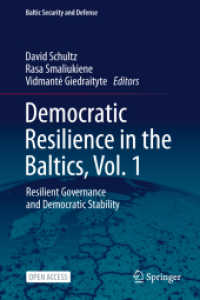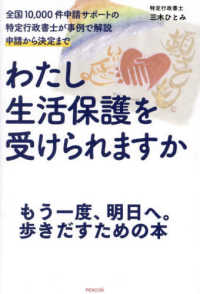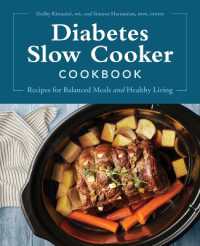- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
出版社内容情報
エリック・バトラー[エリックバトラー]
松田和也[マツダカズヤ]
内容説明
ヴァンパイアはどのように描かれてきたのか。系譜から、吸血鬼の正体に迫る。一七二五年、セルビアの医師フロムバルトが王への報告書に史上はじめてある怪物の名を記した―その名は「ヴァンパイア」。伝承、文学、映画、ジャーナリズム、政治、音楽…あらゆるジャンルで、三〇〇年あまりたったいまでも、その姿をかえながら幾度も私たちの目の前に甦る「吸血鬼」のイメージのすべて。
目次
序 ヴァンパイアの謎と神秘
第1章 不死者の肖像画廊
第2章 ジェネレーションV
第3章 純米国産ヴァンパイア(およびゾンビ)
第4章 吸血の音
第5章 不死への鍵
結語 ヴァンパイア、その表と裏
著者等紹介
バトラー,エリック[バトラー,エリック] [Butler,Erik]
エモリー大学言語学科教授。ヨーロッパの文化や映画についてなど広く論じている
松田和也[マツダカズヤ]
翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
122
つい最近日本語訳されたばかりの本です。ヴァンパイアというとすぐブラム・ストーカーの本か映画を思い出してしまいますが、具体的にどのようなものなのかについてはあまり知りませんでした。その歴史や芸術あるいは社会的な評価などについてわかりやすく説明されていました。一通りの理解は得られると思います。2016/12/08
パトラッシュ
107
東欧の名もなき伝説に過ぎなかった吸血鬼が、なぜサブカルチャーの主要分野を占めるにまで至ったのかを系統立てて解説していく。人の血を吸って永遠の命を得る悪魔の物語を小説や映画で知った一般大衆が、人ならざるものが隣にいるのかとの恐怖に酔いしれたからだ。魅力的な商品であるヴァンパイアを多くの消費者が求め、その需要の高まりが創作者の想像力を刺戟して供給が拡大していった。もし日本におけるヴァンパイア受容に関する項目があれば、欧米と違って漫画やアニメ、ゲームを通じてとされるだろう。そこで特筆されるのは『ポーの一族』か。2022/08/30
HANA
63
初めて文献に出たバルカンの吸血鬼。ルスヴン卿からカーミラ、伯爵を経て最近の作品まで、文学のみならず映画、舞台に至るまで吸血鬼作品を評論した一冊。吸血鬼をセクシャリズム、社会的背景等と関連付けるのはいささか手垢のついた感もするが、本書に至っては著者の吸血鬼愛が文章のそこかしこから透けて見えるので一向に苦にならない。初期の吸血鬼小説は分析も含めて読んだ事が多いので、その後に発生したものやゾンビとの関連が面白かったかな。最近の小説や映画も未見のものが多々あり、このジャンルの魅力を余すところなく伝えてくれた。2016/06/06
めがねまる
31
ヴァンパイアはいつ出現したのか、なぜ恐怖の対象となったのか、今現在のような人気のモチーフになったのはいつからなのか?この本は吸血鬼の発祥から現代に至るまでを、時代背景や民族的な観点、またジェンダーやアイデンティティ、吸血鬼文学の歴史など様々な視座から考察する研究書。吸血鬼という存在(というより現象)が始めて報告された1725年からわずか100年も経たぬうちに吸血鬼は小説と舞台の人気者になり、映画に進出し、最早知らぬ者はいない。けどその正体は?1つ知ったらまた1つ謎が生まれ、何度でも読み返したくなる。2016/08/11
組織液
15
久しぶりに吸血鬼関連の本読みました。神話、文学、映画、報道、ジェンダー、政治風刺、音楽にオペラ、テレビドラマなど、さまざな観点からこの"辺境の怪物"が(特にアメリカにおいて)広まっていた過程を述べ考察しています。翻訳のせいか微妙に読みづらかったのですが、最近の映画やテレビドラマ、小説や曲についてまで書いてあるので非常に良かったです。いきなりポリドリ云々とか出てくるので初心者には向かないですね。『トワイライト』ってやつ読んでみるか…2021/04/21