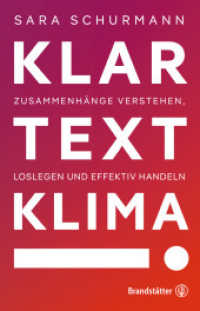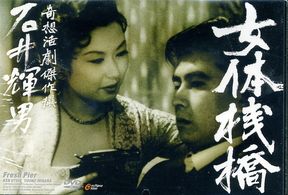内容説明
ドゥルーズやフーコーによる中世・近世の大胆な「誤読」。そこから浮かび上がる“オブジェクト”の謎とその「誤読」の歴史。現代から、デカルトやライプニッツ、スコラ哲学へと源流に向かって遡り、哲学の根本問題の知られざる系譜を描き出す超高密度の思考!
目次
第1章 ドゥルーズと存在の一義性
第2章 フーコーと近世の截断
第3章 ライプニッツと記号論
第4章 ノリスとスコラ哲学の近世
第5章 デカルトとスコラ哲学からの逸脱
第6章 スアレスと対象的概念の系譜
第7章 アウレオリと対象的概念の起源
第8章 オッカムと唯名論の構図
著者等紹介
山内志朗[ヤマウチシロウ]
1957年生まれ。東京大学大学院博士課程単位取得退学。新潟大学人文学部教授を経て、慶應義塾大学文学部教授。専門は中世哲学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
madofrapunzel
3
★★★★★(完読ではない) 中世哲学をほとんど知らない僕は、山内さんのこの本で名前を知ったようなものです。とても面白かった。そもそも現代思想からスコトゥスとかの方へ「逆に」進んでいくというのが親近感がある。マルブランシュあたりの議論で読むのをやめたのですが、またいつか途中を。スアレスとかも気になりました。2014/03/16
ハンギ
3
ライプニッツ研究からドゥルーズ、そしてさらに中世哲学を歩んだ山内志朗氏の本。そんなにわかった気になるのは難しいだろう、話もかなり交錯しているし重複している部分もある。アヴィセンナ、スコトゥス、フォンセカの重要性に力点を置いている。デカルトもライプニッツに引きつけて、唯名論的系譜に出ているし、対象的観念についても論じている。ただ間違えはかなり少ないだろうし、もともと対象的概念は概念ではなく外的事物である、というのは勉強になりました。近代哲学によって媒介は消されてしまったけど、また復活するのでしょうか。2013/12/29
rinrin
0
【BOOK(2014)-021】!!!!!2014/01/30
stray sheep
0
明快にまとめられた思想史のなかに隠蔽されたものを拾い上げて「線香を上げる」営みには個人的にも共感するけれど、半ば自己陶酔的な言い回しが鼻につくこともしばしば。そして本書の内容がタイトル通りであるかについては大いに疑問。誤読に彩られた「対象的概念」の概念史の奥深さは十全に伝わるものの、誤読こそが哲学を駆動するという筆者の主張を支えるには、少なくともドゥルーズ/フーコ以後の哲学的展開に触れるか、より望ましくは概念史的変遷そのものが誤読に突き動かされていたことを示す必要があるのではなかろうか。面白かったけれど。2025/02/07