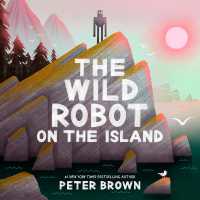内容説明
日本語の起源を弥生時代とする従来の説を排し、その濫觴を縄文時代に求めた本書は、“日本語の誕生”のみならず、いわゆる上代特殊仮名遣い、連濁・四つ仮名現象、アクセントの発生、方言分布など、日本語学における難問をここに解き明かした。記念碑的労作。
目次
第1章 縄文文化―考古学の立場から
第2章 縄文人―人類学の立場から
第3章 日本語系統論
第4章 縄文語の復元
第5章 弥生語の成立
第6章 縄文語の形成
著者等紹介
小泉保[コイズミタモツ]
1926年静岡県生まれ。2009年死去。東京大学文学部言語学科卒業。文学博士。大阪外国語大学教授、関西外国語大学国際言語学部長、同名誉教授を歴任。日本言語学会会長(1988‐91年)、日本音声学会会長(1995‐98年)。ウラル語諸語について比較言語学による分析を行なうとともに、一般音声学、音韻論、語用論に関する理論の研究とその応用を手掛ける。また従来の日本語系統論を批判し、日本語の諸方言に比較言語学の手法を適用して、日本語の祖先に相当する縄文語の再構に取り組むなどの業績がある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Shinji Nakahara
0
縄文語を分析するにあたって現代の方言の音便から当たっていく方法は乱暴な気がした。2014/12/20
むらて
0
1998年上梓。比較言語学の方法論は何が正しく何が違っているのかさっぱりわからないが、源日本語は渡来の弥生語を源流にするものではなく縄文語を基調に渡来語の影響が加味されたもの、という考察は面白く読めた。次はこの本が出て以降の考古学的科学的発見などを加えた現在の源日本語に関する論考が知りたい処です。遺伝子情報研究とか目覚ましくて新たな発見とか次々塗り替えられてるから特にね。それにしても新装版、まして学術系の書籍なら、もっとちゃんと原書発行年を明示するのが当然と思うが如何でしょう。小説だってそのくらいするぞ。2014/09/09
らすた
0
読んだというのがおこがましいほどの飛ばし読みでした。 前半は面白く読めたものの、本格的な言葉の話になると、はるか遠くの国のマイナー言語との発音比較が延々続き、正直よくわかりません。しかし、今では知りえない過去をこんな形で解き明かそうとしている人たちがいるということ自体は非常に興味深く、新たな視野の広がりを得られたように思います。2020/11/06