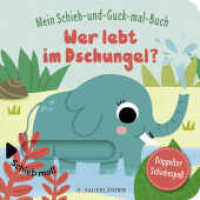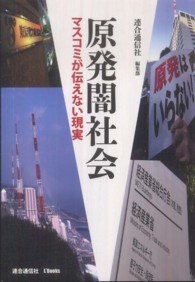内容説明
ソーシャル・ネットワークをつうじて、次々と新たなムーヴメントが起こる音楽シーンを全方位レヴュー。コンテンツの現在を大胆に描き出す。
目次
序章 祝祭の風景の一九六〇年代とゼロ年代以降
第1章 ガジェット化する音楽
第2章 キャラクターをめぐる人形遊び
第3章 ライヴ感の共同体のなかのライフ
第4章 音楽遊びの環境
第5章 浮遊する音楽論
終章 繰り返されるトランスフォーム
著者等紹介
円堂都司昭[エンドウトシアキ]
1963年生まれ。文芸・音楽評論家。1999年、「シングル・ルームとテーマパーク―綾辻行人『館』論」で第6回創元推理評論賞を受賞。2009年、『「謎」の解像度―ウェブ時代の本格ミステリ』(光文社)で第62回日本推理作家協会賞と第9回本格ミステリ大賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
サイバーパンツ
20
SNSの発達したゼロ年代以降の国内ポップ・ミュージックを「聴取」から離れた場所で起こる「遊び」や音楽を通した人々の「つながり」の方に重きが置かれていると分析。音楽を取り巻く環境を含む「ミュージッキング=行為」的な見方をしなければ捉えきれない音楽のあり方を包括的に考察しており面白い。アニソンの歴史性欠如、未整理な断片的表現のネットワーク化を成すやくしまるえつこと神聖かまってちゃん、つながりの再確認に使われるロキノン批判などについて書かれた浮遊する音楽論が特に秀逸。2019/01/07
センケイ (線形)
6
かなり網羅的で、まとめとしての価値が高く感じられる。直近の動向だけでなく、雑誌文化からの系譜が事細やかに述べられている点も嬉しい。さらに言えば、アイドル、バンド、(無料)配信といった個別の動向について、Web 2.0 以前からあった流れをどのように組み受け、それが現在においてどう展開されているのかについて連続的に書かれている。新しい演奏のされ方、新しい聴き方が古くからなされてきたという全体の流れが分かる一方で、個別の興味に着目する上でも、よく理解を整理できる有難い構成になっている。2019/10/19
鳩羽
5
自分の好きな音楽やアーティスト、そこから何を得たいのか、どんな楽しみ方をしたいのかということを考えさせられる。遊ぶための道具、場所、遊び仲間がそろえば、それは遊ぶだろう。音楽を聴く耳、踊る身体、発信する言葉。個人がそのままつながりの中での、楽器の一つになるかのようだ。優れた製品が提供されるはずというのは幻想で、それこそ崩壊した大きな物語の一つなのかもしれないけど、芸術やそれに準じるものはなにかすごいものであってほしいという、そういう寄る辺ない寂しさも感じる。2013/03/11
unterwelt
4
2013年刊行。5年前の本なので今取り上げるとしたらiTunesStoreじゃなくてSpotifyだよなぁ、と思ったりもしますが、書かれている状況は古びていないように思えました。作品を鑑賞したり作品を通して作者の思想を理解することよりも、作品を通じてつながったり作品で遊んだりという事の方が優位に立っているという状況。ただ今の状況は急に出てきたのではなく、昔からそういうことは起きていたというのも興味深かった。あと個人的にはアイドルやアニソンにも触れているのがよかった。2018/06/10
霧
4
薄いといえば薄いけれども、一応いろんなものを読み、包括的に考えているということには敬意を表したい。ロックを聞いてきた大の大人がネット時代の音楽を自信をもって語るのは勇気あることだと思う。2016/09/05