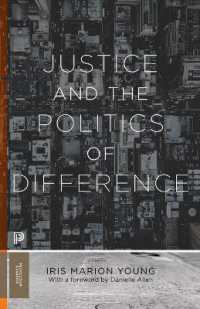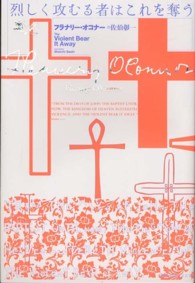内容説明
日本仏教の大きな特徴にして到達点とされる「肉食妻帯」はいかにして形成され、定着したのか。国家宗教として仏教が日本にもたらされてから孕みつづけている最大の問いを考究し続けた著者の研究成果のすべて。
目次
第1部 肉食妻帯と日本仏教(女犯肉食と肉食妻帯の距離;肉食妻帯;“日本仏教”の発生―肉食をめぐる禁忌の形成に関連して;「仏教の日本化」をめぐって)
第2部 肉食妻帯と近代仏教(「おのづから」と「無戒」―「肉食妻帯」に見る日本人の宗教意識;「肉食妻帯」問題から見た日本仏教;日本の仏教にとって「肉食妻帯」とは何だったのか)
第3部 殺生と肉食(殺生罪業観と草木成仏思想;東国教団における「悪人」たち;「血食」とカニバリズム―折口信夫の貪婪と快楽;不殺生戒と動物供犠)
著者等紹介
中村生雄[ナカムライクオ]
1946年静岡県生まれ。1969年京都大学文学部卒業。静岡県立大学国際関係学部教授、大阪大学大学院文学研究科教授、学習院大学文学部教授を歴任。専攻は日本思想史・比較宗教学。2010年逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ネギっ子gen
56
【なぜ日本では出家した者が、妻を娶り肉を食べるのか】国家宗教としての仏教が日本にもたらされてから孕み続けている最大の問いに迫った、日本仏教の大きな特徴にして到達点とされる「肉食妻帯」がいかにして形成され定着したかを解析した書。著者の逝去後、この論考集を編んだ三浦佑之教授は「あとがきにかえて」で、こう書く。<日本仏教について、ことに近代の日本仏教について、中村さんは大きな疑問を抱き続け、問い続けてきた。そしてそれは、現場の僧侶にとっては、ふれることさえはばかられる大きなタブーであり続けた、そして今も>と。⇒2024/01/19
南北
41
江戸時代までは浄土真宗と修験道を除いて僧侶が妻を持つことは建前としてはなかったが、明治時代以降、太政官布告によってなし崩しに容認されるようになってきた。「肉食妻帯」に迫るには親鸞や「在家法師」などさまざまな論点からの解明が必要となる。遺作のため、これに続く論考が望めないのは残念だ。仏教各派も宗祖の教義と矛盾する点を曖昧にしたまま「肉食妻帯」を行ってきたところもあり、内容によっては妙なところで反発を受けるかもしれないと思うが、今後とも研究が進められることを期待したい。2021/01/20
ハチアカデミー
20
本来の仏教思想からは禁忌されてきた「肉食」「妻帯」のふたつが、なぜ日本社会では常態となっているのかを、仏教思想の受容を辿りつつ考察。日本が近代化する中で、かつては異端とされてきた親鸞を教祖とする真宗派が急激に勢力を伸ばす。その背景にあったのが、この「肉食妻帯」である。社会が要求した価値観にぴたりと合う思想だったのだ。キリスト教がプロテスタンティズムによって一般に広がったように。自明を疑うことから歴史学は始まるのだと言うことを強く感じる一冊である。日本人の草木観に切り込んだ「殺生罪業観と草木成仏思想」は白眉2014/03/25
kenitirokikuti
8
「肉食妻帯」という語は、明治5年の太政官布告に現れるもので、仏教用語ではない。日本の僧は実質的な「妻」を持つことはあったし、「僧」という制度自体が形骸化している部分もあった。近世の真宗内部で、親鸞は観音の化身であり、妻を得たのも在家往生を示すため、みたいな理屈▲律令の殺すな規定は殺人に関するもの。仏教の殺すなは有情(生き物)に対するもの▲石川啄木は明治18年生まれ。僧の「肉食妻帯勝手」(および姓を得る、畜髪する)布告から10年以上が過ぎているが、啄木が生まれたとき彼の母は入籍していない2019/08/27
gryphonjapan
4
実にわらってしまったのは「魚の側が『偉いお坊様に食べてもらえれば私は功徳になってありがたいのに、食べてくれなくては困ります』と言い出し、なるほどと坊さんが魚を食べる」という説話。ご都合主義杉(笑)!!¥だが思想的な意味も確実にあるのだ。妻帯にかんしては浄土真宗の問題だけにとどまらないということがわかった2012/12/02
-

- 和書
- イエスさまがうまれた