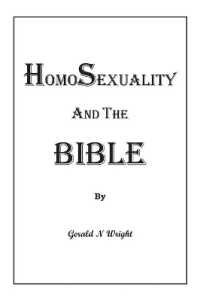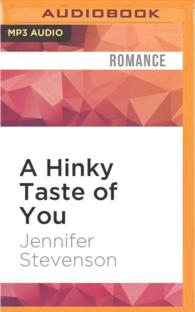内容説明
将棋の王様・阪田三吉の軌跡と大大阪の空間性、新世界の荒廃と飛田遊廓、ジャンジャン町の隆盛。産業資本と大阪政界の思惑の一方で、借家人同盟、野武士組、女給たちが立ち上がる…塔のみえる場所で、人々は彷徨い、遊び、闘い、そして何を生んだか?圧倒的密度で描く、大阪ディープサウス秘史。
目次
第1章 ジャンジャン町パサージュ論(新世界!新しい世界!;抗争、新世界;水漏れする装置)
第2章 王将―阪田三吉と「ディープサウス」の誕生(阪田三吉のモンタージュ;夕陽丘の将棋指し;将棋の王様)
第3章 わが町―上町台地ノスタルジア
第4章 無政府的新世界(借家人同盟、あらわる;Trans Pacific Syndicalism/Trans Pacific “New World”;借家人の精神からの社会的なものの誕生)
第5章 飛田残月(湿った底に;敷居の町)
著者等紹介
酒井隆史[サカイタカシ]
1965年生まれ。早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻博士課程満期退学。現在、大阪府立大学人間社会学部准教授。専攻は社会思想史、社会学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
38
大阪、それも新世界、飛田という濃い地域を主に大正期の変化を論じている。各章ごとにその地域と著名人、坂田三吉、宮武外骨や社会主義者達を点描しながらその特異性を浮かび上がらせる手法を取っていて読んでいて実に面白い。語られている事も新世界が昔から盛り場だったと思っていたら人工的に作られたものという事だったり、宮武外骨と赤新聞の事だったり、大阪の社会主義者達の動きだったり、どれを取っても凄く読み応えがある。ただ僕はなんば以南に行った事がないため、地名と位置関係がよくわからなかった。一度通天閣行ってみたいなあ。2013/03/22
kokada_jnet
36
第二章の、阪田三吉の、実像と、フィクションに描かれた彼についてを読んだ。非常に丹念な調査で、将棋ファンにもよませたい内容。現代思想系の書き手が、ここまで事実を調べまくって、大著を書いているのがすばらしい。2018/05/14
きいち
26
満腹した~。鞄の中に700頁を越えるこの重い本をほぼひと月持ち歩いてしまった。量もだけど、密度がすごい。◇大正期に誕生し戦時中に消失した初代通天閣を狂言回しに、伝統から切れ無包摂の状態になった人々が吹き寄せられた新世界、そしてその南の飛田、北の日本橋周りを追う。主役は場所だ。王将・坂田三吉や宮武外骨らも十分良いが、誰よりも魅力的だったのは逸見直造という陽性でハッタリのきいた怪しくもアナーキーな社会運動家。著者の筆も走る走る。◇紹介される数多くの映画、酒井の批評が映画の画面そのものを向いてて、これも素敵だ。2014/08/25
Bartleby
14
分厚くて読みごたえがある。大阪に行き初めて通天閣というものを見て、またその周辺の独特の活気が面白すぎて、俄然知りたくなった。本書は通天閣が建つはずの場所周辺にいたいわゆるアウトサイダーと呼ばれる人たちの闘争の歴史、そして資本主義の潮流へのしたたかな便乗の歴史を描いている。いずれにしても嫌な気はしない、これが生きるということなのだといずれにも共感を寄せる。知れば知るほどに愛おしく思えてくる。底に流れるえもいわれぬ哀しみも含めて。得体の知れない人やノイズがたえず出入りしている、という川島雄三の形容がぴったり。2023/01/08
1.3manen
9
副題からすると山田盛太郎を想起。歴史社会学的でもあり、まるで辞典。地元学と位置付けてもいいか。阪田三吉の将棋人生(235ページ)。下戸、芸妓恐怖症の人だったという(277ページ)。水島新司『ドカベン』の通天閣高校4番エース坂田三吉は漢字が違っている(278ページ)。引用される人物として、故藤本義一氏らが出てくる。文献は『川島雄三、サヨナラだけが人生だ』の中で故小沢昭一氏との対談があるという。情報としてメモ。経営家族主義。懐かしい響きで産業社会学概論の講義で聴いたな(446ページ)。宮武外骨『滑稽新聞』も。2013/02/20