内容説明
前福島県知事と気鋭の社会学者が、これからの「日本」について徹底討議する。あらゆる「中央の論理」から自立し、「地方」だからこそ可能な未来を展望し、道州制から環境問題、地域格差まで、3・11以後の社会のありかたを考えるいま必読の書。
目次
はじめに 3.11以後、私たちは何を語れるのか
第1章 3.11以後から考える(エネルギー政策と地方;震災後の対応をめぐって;トカゲのしっぽきり ほか)
第2章 めざすべき地方の姿を考える(いま必要とされているリーダーシップとは何か;本当の保守主義とは何か;安積艮斎と安藤昌益に学ぶこと ほか)
第3章 「地方のみらい」を考える(二一世紀は福島の時代;民主主義をめぐって;一極集中からの脱却 ほか)
あとがき 地方の論理こそが国際標準
著者等紹介
佐藤栄佐久[サトウエイサク]
1939年福島県郡山市生まれ。東京大学法学部卒業後、日本青年会議所での活動を経て、1983年に参議院議員選挙で初当選。87年に大蔵政務次官。1988年から2006年まで福島県知事を務める
開沼博[カイヌマヒロシ]
1984年福島県いわき市生まれ。2009年東京大学文学部卒。2011年東京大学大学院学際情報学府修士課程修了。現在、同博士課程在籍。専攻は社会学。著書、『「フクシマ」論』(青土社、2011年)で第65回毎日出版文化賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
17
対話集。 佐藤氏=S。開沼氏=Kとしよう。 S:核のごみ捨て場と化すようなことは困る(27頁)。 後から後から出てくるごみ置き場の問題が被さってくる。 K:中央(東京)の側には他人事の感覚、地元のことは二の次、 という地方軽視の感覚がある(44頁)。 だからこそ、舛添氏が脱原発候補を破ってしまったのだ。 困ったことである。 まだ、病人が目に見える形で数年後に出ないと反省しないようだ。 水俣や沖縄の事例もある(51頁)。 本社と支店のようは中央省庁と地方自治体の関係(65頁)。 2014/03/31
hwconsa1219
1
佐藤元福島県知事と気鋭の若手研究者による、福島から考える日本の未来像を語る対談です。 この本における地方の論理…地方が地方のままで生きていける、競争からこぼれる者を如何にしても救う、という、弱者切捨でない「共々に生きて行く」論理。勉強になりました。2012/09/03
遠山太郎
1
「フクシマ」のこれからより、フクシマを知るために。条例にもとづくうつくしまふくしま、IT化をみこし7割外国人講師の会津大学、県を生活圏で分析した共生のための開発政策、県立高校共学化。佐藤栄佐久の地方の論理は多様性もってけっこうやった的な。 移住といってるだけじゃなくて・・に深く同意。地方は出るのは簡単で、入るのは難しい。都会はまとめて本書の指摘からいっちゃえば、ビル乱立・物価高い・超満員電車。田舎の空いてる土地に安く住ませる、一定の自給自足まで支援とかやったらいいのに。2012/06/25
psi_x
1
多様性を尊重してどう自分たちが住む地域をより素晴らしいものとするのか。自ら考え国と対峙する姿勢は忘れてはならないのかな。2012/03/18
-

- 電子書籍
- えっ、能力なしでパーティ追放された俺が…
-

- 電子書籍
- Dr.コトー診療所 新装版 12
-
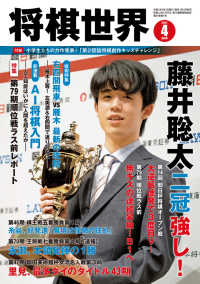
- 電子書籍
- 将棋世界 2021年4月号 将棋世界
-
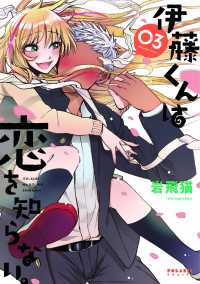
- 電子書籍
- 伊藤くんは恋を知らない。(3) ポラリ…
-
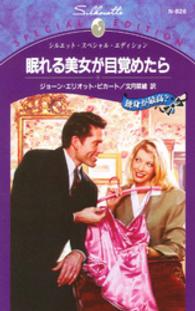
- 電子書籍
- 眠れる美女が目覚めたら 独身が最高? …




