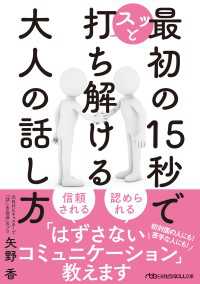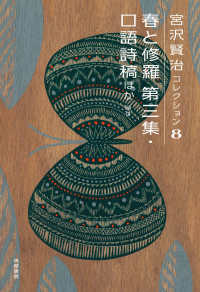内容説明
「母なる地球」での共存共栄は幻想にすぎず、むしろ生命は互いに凄惨な共倒れを繰り返してきた。この星は、いわば「死を招く母」である―。注目の生物学者が大胆な仮説によって提示する、生命40億年史の衝撃的な真相。
目次
第1章 ダーウィン的生命
第2章 進化における「成功」とは何か
第3章 地球上の生命に関する二つの仮説
第4章 メデア的フィードバックとグローバルな過程
第5章 生命の歴史におけるメデア的現象
第6章 メデアとしての人類
第7章 時間を通して検証される生物総量
第8章 予測される生物総量の将来動向
第9章 要約
第10章 環境主義の含意と行動方針
第11章 何をなすべきか
著者等紹介
ウォード,ピーター・ダグラス[ウォード,ピーターダグラス][Ward,Peter Douglas]
古生物学者。ワシントン大学教授(生物学、地球・宇宙科学)。「地球生命の定義」や「大量絶滅」といったテーマを切り口に幅広い執筆活動を続けており、TVでの活躍も多い
長野敬[ナガノケイ]
河合文化教育研究所主任研究員。自治医科大学名誉教授。生物学・生命論専攻
赤松眞紀[アカマツマキ]
自然科学系の翻訳に携わる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hsg
2
ガイア仮説とそれに基づく盲目的な環境保護主義や,それから派生したニューエイジ的な考えを批判し,生命は基本的に個体の生存と増殖しか考えていないことから,それ自体最終的に自身の生存に適した環境の破壊をもたらすと主張する一冊.自身の生存に適さない環境下で,環境に合わせてダーウィン的進化により適応する真核生物に対して,化学物質の放出などを通して環境の変革を試みる原核生物という対比を出し,その意味で人類は原核生物的であると述べているのが面白いと思った.2018/06/07
GASHOW
2
地球はこれまで5回くらい隕石由来の大量絶滅を経験している。隕石がない、スノーボールという地球の凍結の生命の絶滅もある。外的要因だけでなく、人類が滅ぼすことも可能なのだと思った。2014/03/04
原玉幸子
1
地球上の生命体に関わる炭素や気温は、海水や太陽エネルギー他の「大きな枠組み」の中で調整されており、その循環や調整機能の仕組みこそが生命(体)であるとの説が『ガイヤ仮説』で、地球の過去の地殻・気候変動の全ては生命体を常に絶滅の危機に晒して(生命は辛うじて生き残って)来たとの逆の見解が著者の主張する『メデア仮説』です。科学的見地から読み込もうとすると退屈ですが、何に惹かれ何に怯えているのだ、との哲学・宗教的感覚を意識しつつ小説として読めば(SFっぽいところもあり)面白いです。(◎2017年・夏)2020/02/11
47
1
自然に還る事で果たして本当に地球は、生命は生き残れるのか。そして還るべき自然とは一体何処にあるというのか。増え続ける人類はかつての微生物と同じ道を辿るのかどうか、文明の発展の先に何があるのか。みんなが同じ想いを共有する前に、取り返しの付かない線を超えてしまうのか。考えさせられる。2011/12/07
YTY
0
地球史における大量絶滅事件やWalker Feedbackの話が主で、意外とまともな内容だった。2011/04/11