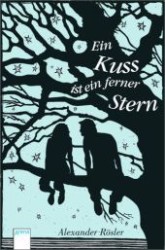出版社内容情報
本書はポストフォーディズム期における新たな労働生産モデルを提示しようとする野心的著作。
内容説明
世界規模で激変する社会の中で労働は大きくそのかたちを変えた。コミュニケーションと労働の結びつきが、働くという概念を劇的に変え、すべての労働が感情労働化し、非正規雇用化することを喝破した画期的名著。
目次
第1章 労働からの再出版=再配分(リーン生産方式;メイド・イン・ジャパン;イノベーションと政治形態 ほか)
第2章 無規範と規則(意味の市;ソックスの場所;情報経済における価値 ほか)
第3章 国家と市場(クリントン政権の限界;中産階級という理念;国家と市場 ほか)
著者等紹介
マラッツィ,クリスティアン[マラッツィ,クリスティアン][Marazzi,Christian]
1951年、スイス生まれ。パドヴァ大学政治学科卒。ロンドン大学経済学スクールに留学し、ロンドン市立大学経済学科で博士号取得。現在、スイス=イタリア専門大学(SUPSI)の社会経済研究所の教授
多賀健太郎[タガケンタロウ]
1974年生まれ。大阪大学大学院講師。哲学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
非日常口
10
論理的に話すということは企業内に組織を生み出すための言語だ。フォーディズムからトヨティズムに時代が移行した時、量から質を求められるようになった。だが、効率化しても給与や時間は増えただろうか?脂肪を敵視する私たちは健康のためというが、企業の感覚が日常に浸食したのかもしれない。本書はJITがトップダウンから細分化されたプロセス/責任をネットワークが繋ぎ、各部長同士のコミュニケーションによる相互依存/監視状態になったことを指摘する。トップはそれを遠くから眺める。心すら労働になる時代の到来。イイネはイイの?2013/12/16
ゆう。
5
僕の勉強不足からか、あまりよく理解できなかった。ポスト・フィーディズム期の労働のあり方はを論じ、警鐘を鳴らしているのだと思う。生産様式がフレキシブルになり、コミュニケーションの役割が中心に位置づいていくと述べているが、なかなか展望がみえてこなかった。経済学がわかっていないからダメなのかなぁ((+_+))2014/03/29
roughfractus02
1
ポストフォーディズムは50年代に出現したトヨタ方式に始まるという著者は、生産滋養教を経営側だけでなく労働者が判断し、相互コミュニケーションによって調整する。個々の時間のみならず感情が労働化するこのような「認知資本主義」世界では、生産目標が短期変動するので、労働力も抑えられる(非正規雇用の拡大)。またコンセンサスを常に促すので経済と政治の敷居が低くなり、経済的自由主義が国家の根幹に介入する。経済の「言語論的転回」はIT導入の前に我々の言語使用の問題であり、サービス労働が増えるWWⅡ後から検討する必要がある。2017/02/15