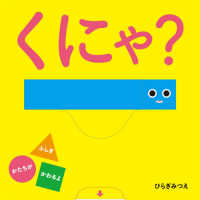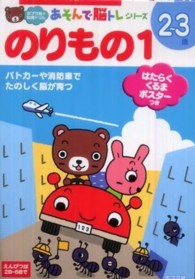出版社内容情報
イスラム国家インドネシアでなぜバリだけがヒンドゥ教なのか。少数派宗教への統治政策から近代・宗教・国家をとらえおす。
内容説明
イスラム教国インドネシアでなぜバリだけがヒンドゥー教の島なのか。植民地国家から国民国家への連続性のなかで実体化される制度。あまりに自然化された「伝統」への疑問を基底に、少数派宗教への統治政策から近代・宗教・国家をとらえなおす。
目次
第1章 王国・帝国・ヒンドゥー
第2章 定義される本質、崩壊する宇宙
第3章 もうひとつの空間
第4章 社会復興と道徳
第5章 国家と宗教
第6章 新秩序の精神
第7章 魂のゆくえ
終章
著者等紹介
永渕康之[ナガフチヤスユキ]
1959年生まれ。文化人類学。ウダヤナ大学(バリ)留学、大阪大学大学院人間科学研究科後期課程退学。カリフォルニア大学バークレー校、ライデン大学客員研究員を経て、名古屋工業大学大学院工学研究科教授。主な著書に「バリ島」(サントリー学芸賞受賞、講談社)ほか(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえ
6
「バリ社会の宗教制度の基本構造は、植民地近代において宗教的権威があらたに承認され、同時にブサキ寺院という中心寺院における儀礼を宗教的権威が再構成して教義上の真理と結びつけ、政治的中心が執行する体制が成立し、現在にいたるまで継承されたその過程にある…植民地統治にはじまる近代は世俗化を意味するのではなく、むしろ近代において宗教制度が再生産されたのである。しかもそれは、バリ人が確固とした宗教意識を持ち、植民地国家から国民国家へ変遷するなかでそれを堅持したためではない」2019/02/19
toiwata
1
「イスラム教国インドネシアでなぜバリだけがヒンドゥー教の島なのか」の惹句が大変端的。バリ島で済州島のような悲劇があったことをこの本で初めて知った。「新編国家神道とは何だったのか」とあわせて読むと日本語が母語のひとは思うことがいろいろあるのでは。2016/04/03