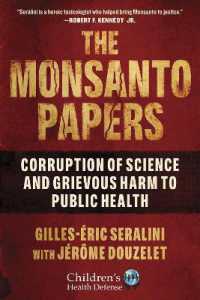内容説明
いつまで経ってもカウチから起き上がってこない息子を前にして、とうとう私はキレた。と同時に、人類と労働に関する歴史を遡る決意をしたのだった。私たちは、なぜ働かない人に対して怒りを感じるのか。パウロの書簡「働きたくない者は、食べてはならない」から、情報社会の怠けものまで―。数々の文学・映画作品、社会学・心理学のデータを駆使して綴られた、壮大なる「労働文化誌」。
目次
第1章 カウチの上の息子
第2章 怠けものとその仕事
第3章 放蕩者/ロマン主義者/アメリカの浦島太郎
第4章 のんびり屋/共産主義者/酔っぱらい/ボヘミアン
第5章 神経症/散歩者/放浪者/フラヌール
第6章 遊び人/フラッパー/バビット/バム
第7章 ビート/反=体制順応主義者/プレイボーイ/非行少年
第8章 徴兵忌避者/サーファー/TVビートニク/コミューン・ヒッピーたち
第9章 情報社会のスラッカー―働く倫理と働かない倫理
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
白義
19
怠け者の思想、文化がどのような歴史を辿ったかを特にアメリカの文化史から紐解いた、タイトルのわりに労力を注ぎすぎてる感のある本。ジョンソンからワイルド、ケルアックに、ボヘミアンやヒッピー、ハッカーまで、いや働きたくない!という一言をこれほどまでに作品にし、また思想的に正当化してきた人々の多さ、文化の厚みには脱帽するばかり。特にアメリカと日本は勤労と怠惰のカルチャーが二極はっきりした社会なのだそうな。確かに、本書の冒頭で語られる著者親子のお話は、日本のことだと書いても全く違和感がない2012/09/20
わん子
18
産業革命以降の「働かない」人たちの記録を時代順にまとめ、追った労働文化史。資本主義が求める労働力=決められた時間と場所に押し込められ「生きるために働く」のでなく「働くために生きる」あり方へ人間性の変質を強要する資本主義社会への抵抗の軌跡が描かれている。しかし徐々にそのあり方も周縁に追い詰められる印象を受けた。 また、本書で取り上げられている働かない人たちのほとんどは男性で、その放蕩ぶりを支えていたのはおそらく女性の無償労働であろうと想像すると「働かずに抵抗すること」すらも男性の特権なのかと思われた。2018/04/26
にしがき
13
👍👍👍 18世紀から現代までの、米国(+欧州少し)の働かない人たちの文化史。働くことを良しとしなかったり、働いていると言いつつ働いていなかったり、仕事がなかったり 等々。経済や産業をあくまで背景として、小説、記事、音楽、映画 から、その時々の人たちが労働をどう捉えていたかを時代ごとに描写する。「働かない」を考えることで「働く」とは何かが見えてくる。 労働倫理の移ろいに驚きつつ、著者の挙げる例の多さに圧倒された。 個人的に、60年代以降が馴染みが出てきて読みやすくなった。2021/02/13
greenman
11
これは傑作としか言いようがない。ニートや働きたくない人どころか、働くことを考えるすべての人へ影響を与える凄みがある。特に人生において合理的や夢に一直線に行動する人よりも、人間に対してマイナス面を見つめる人や、人生をさすらう人達には一度読むべきだろう。いや、夢を持っているけれどそれが世間であまり認められていない人にもオススメできる。ビートニク、ヒッピーなどの流れ者に似た、日本の書物はどういうものがあるだろうか。ぼくは網野善彦の「無縁・公界・楽」での中世の遊行者たちと似ている点があるように感じた。2011/06/20
rubeluso
4
日本語タイトルに反して、真面目に「労働に」ついて考えてきた人々の記録。主にテレビや映画を含む文学作品を通して、積極的に「労働」をしないことを主張してきた人々がいたということを知ることができる。この本で登場する人々は多かれ少なかれ積極的に働かないことを選択した人々である。それゆえに、何も書き残さず、社会に自分の痕跡を残そうとすらしない真の「怠け者」や、あるいは反社会的な立場ゆえに「怠け者」とされた人々のことは知ることが出来ないのが物足りなかった。2018/01/31