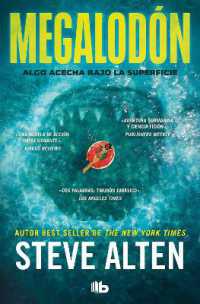内容説明
戦前の帝国体制と戦後の文化体制の綴じ目から這い出してくる亡霊とは何か。文学作品に散種された帝国秩序の抑圧と狂気と暴力を顕在化し、谷崎潤一郎・安部公房・目取真俊など、作家の抵抗と失敗の徴を透視する。
目次
帝都への抵抗―谷崎潤一郎1933『春琴抄』
帝都の人造怪物―内田百〓(けん)1934『旅順入場式』、1938『東京日記』
戦時下の国民作家―太宰治1936「思い出」、1944『津軽』
植民地の亡霊―安部公房1948『終りし道の標べに』、1957『けものたちは故郷をめざす』
戦争の継続状態としての「戦後」―開高健1959『日本三文オペラ』
植民地下の「狂気」の由来―島尾敏雄1960‐77『死の棘』、島尾ミホ1987『祭り裏』
帝国主義日本の「法の外」―梁石日1992『子宮の中の子守歌』
死者に触れる技法―目取真俊1997『水滴』、1999『魂込め』、崎山多美1999『ムイアニ由来記』
著者等紹介
丸川哲史[マルカワテツシ]
1963年、和歌山県生まれ。一橋大学大学院言語社会研究科博士課程修了。現在、明治大学政治経済学部教員。主たる専門領域は、日本文学評論・台湾文化研究・東アジアの文化地政学。小倉虫太郎の筆名ももつ
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。