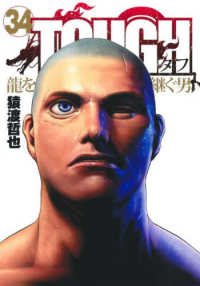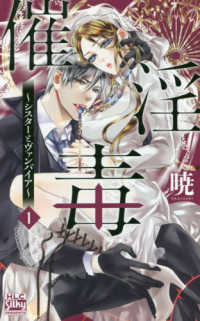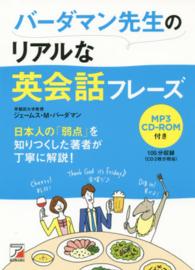- ホーム
- > 和書
- > 芸術
- > 演劇
- > オペラ・ミュージカル
内容説明
ブルジョア階級の抬頭そして現代音楽の出現と、二度も息の根を止められたオペラ。だが不死鳥の如く蘇るオペラの強靱な生命力の源泉とは―。モーツァルトとワーグナーを対照し、音楽の輝かしく豊かな可能性を、現代思想最先端の眼差しで解明する。オペラへの限りない愛の成果。
目次
ムラデン・ドラー(音楽が愛の糧であるならば)
スラヴォイ・ジジェク(「私はその夢を、見たくて見たのではない」(「昼が考えたよりも深い」;「共同体永遠のアイロニー」;女性的過剰;走れ、イゾルデ、走れ))
著者等紹介
ジジェク,スラヴォイ[ジジェク,スラヴォイ][Zizek,Slavoj]
スロヴェニアのリュブリアナ大学教授。ラカン派マルクス主義者として、その多彩な活動は世界の思想界で注目を浴びている
ドラー,ムラデン[ドラー,ムラデン][Dolar,Mladen]
スロヴェニアのリュブリアナ大学哲学教授
中山徹[ナカヤマトオル]
1968年生まれ。筑波大学大学院博士課程文芸・言語研究科単位取得退学。英文学専攻。現在、静岡県立大学短期大学部講師
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
oz
3
初読。終焉が宣告された数多の芸術の中で、オペラだけがなぜ藝術音楽の最高峰という特異な地位にあり続けるのか?という問いから始まるオペラ論。音楽を愛好した哲学者は数多いがオペラを愛好した哲学者はニーチェなど数えるほどしかいない。それはオペラが上っ面の美しさに存在の全てを賭けた芸術であるためだ。そんな虚飾の芸術オペラの歴史をモンテヴェルディ・モーツァルト・ワグナーの三大転換点に着目しながら辿る。オペラの勉強に本書を用いるならば当然ながらジジェクさんではなくドラーさんの章から読みましょう。2010/01/12
またの名
2
前半は、ジジェクトロイカの一端を担うドラーが議論の叩き台となる枠組みとモーツァルトについて論じる。メインになるのは慈悲の論理の推移。もちろんそこにイデオロギー分析もついてくる。後半のジジェクはいつものように雑駁な議論と低俗な小ネタを繰り出しつつ、ワーグナーの読解を議論の中心に据える。『否定的なもののもとへの滞留』とかぶる部分が多い。ドラーで丁寧に議論の骨子を固め、それをジジェクでぶっ壊して様々な方面に拡散していくような展開をしている。してその主張は?となると、金太郎飴なのは否定できない。面白いのだけどね。2012/12/30
-

- 和書
- カルマは踊る