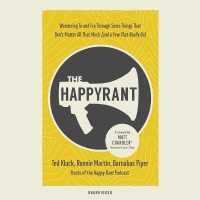内容説明
パンのみにて生きるにあらず。見てくれ悪く素っ気ない、食卓の花形にはなれないじゃがいも。だが、度重なる大飢饉救済に、産業革命の労働者の活力源に、新大陸開拓農民の慰めとして、また王侯貴族の精力剤として、じゃがいもは大活躍だった―。歴史変革期の蔭の実力者じゃがいもが数々のドラマで織りなす初の社会文化史。
目次
アンデスの宝―ペルーとヨーロッパ 1550‐1650
哀れな人たちの慰め―アイルランド 1650‐1800
中流以上の人々―イングランド 1650‐1800
土に生るリンゴ、万歳―フランス 1650‐1800
独立アメリカ合衆国の食卓―独立以前のアメリカ 1685‐1800
やつは首吊りだ―イングランド 1800‐1900
包囲された砦―アイルランド 1800‐45
倹約一路―フランス 1800‐1914
ランパー芋は真っ黒―アイルランドの大飢饉 1845‐49
じゃがいもと人口―イングランドとアイルランドの人口激変
女の仕事―アメリカ合衆国 1800-1914
良い仲間―イングランドのフィッシュアンドチップス
出自の貴賤
著者等紹介
ザッカーマン,ラリー[ザッカーマン,ラリー][Zuckerman,Larry]
平和活動ボランティアとして中央アフリカ共和国の中学校で英語を教える。その任務の後、料理訓練プログラムの責任者となる。現在は執筆活動に専念。シアトル在住
関口篤[セキグチアツシ]
1931年生まれ。詩人・英文学者
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
シルク
11
むかし、子ども向きに書かれた『レ・ミゼラブル』を読んで、生唾ごっくんとなった箇所があった。悪党が、ジャン・バルジャンから搾り取ってやろうと、仲間のワル数人を応援に誘いリンチの準備をして待機している場面。悪党が仲間に「何か食ってきたか?」と問うと、仲間は「超絶でかいじゃがいもに、塩をたんまりふって3つ食ってきたぜ」とか言うのだ。……じゃがいもに、塩をたんまり。茹でるか焼いたかしたほこほこのじゃがいもに塩?! 読みながらその時は、ジャン・バルジャンの身を案じることもハラハラも忘れて、御馳走だ~って思った(笑)2017/01/29
Yuri Mabe
4
「世界を救った」「文化史」というより、欧州特にアイルランド限定での話ばかりなので裏切られた感。ロシアやアジアに言及がないままこれだけのボリュームなので相当真面目に書いてある。のはわかるけど読んでて面白くもない…。中世の飢饉の状況やイギリスの囲い込みの背景などはあまりテキストがないところなので珍しい。2015/06/10
sekaisi
3
ポテトチップスを食べながら読みました。2023/08/15
takao
3
では、じゃがいもが普及する前はどうしていたのか?2021/04/13
くさてる
3
じゃがいもという野菜が西欧にとり、どれだけ重要な存在であったかを紐解く文化史。時には珍重され、時には疎まれ、いろんな扱いを受けたけれども、結局は人々を飢えから救った素晴らしい存在だと思った。文中に出てくる当時のじゃがいも料理も楽しかった。2012/04/21
-
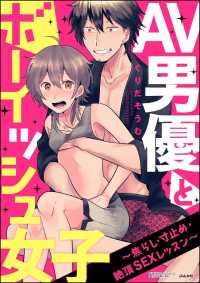
- 電子書籍
- AV男優とボーイッシュ女子~焦らし・寸…