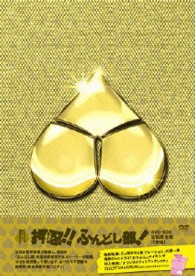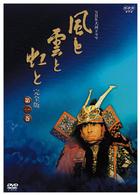内容説明
アリストテレス、仏教論理学、現代の記号論理学を中心に、人類共通の思考の枠組みである“判断”と“推理”を検証し、普遍的論理の構築を目指す。
目次
第6章 判断とは何か―その構成要素(判断;判断と命題;「わかる」と「知る」 ほか)
第7章 推理についての考察(推理とは何か;推理の位置づけ;推理の種類 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あかつや
5
インターネットやなんやで世界とのやり取りが容易になって、それで人類みな兄弟地球一家だ仲良くやろうぜって言ったって、そんなの必ず衝突が起こる。なぜなら人々はそれぞれ違っているのに、みんな同じでわかり合えるんだって思い込んでるから。ところが論理の立て方からしてこんなにも違うのだ。わかり合うためにもまずその違いを明らかにして、きちんと並べて比べてみないことにはお話にすらならない。違いを理解し、基本的部分を曖昧にせず、しっかり学問として構築する。この本はその重要な仕事に果敢に立ち向かっていった人の偉業だと思った。2021/11/01
roughfractus02
4
上巻終盤の「思考の原理」では矛盾律・排中律・因果律に関する西洋圏とインド圏の違いが指摘された。矛盾・排中の2律(law)に注目する西洋に比べ、東洋(インド)はさほど重視しない点を受けた下巻では、東西の論理の判断と推理が分岐していく様を、ギリシャ・インドを起点とするインド・ヨーロッパ語族圏外の中国や日本まで描く(論の内容は『中国人の思惟方法』『日本人の思惟方法』を受け継いでいる)。真偽をベースに数理論理化する西洋が、個を強化する一方、真偽の争いの外に出ようとする東洋は、個を作る言語の外に論理を対峙させる。2021/04/07
-
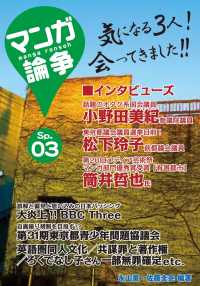
- 電子書籍
- マンガ論争SP 03 オーシャンブックス