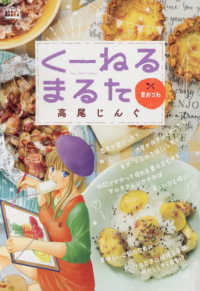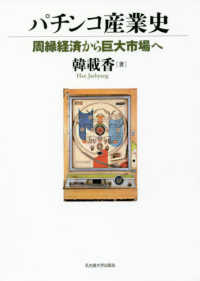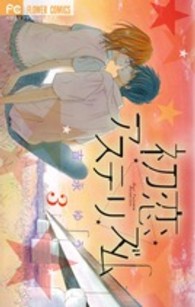内容説明
戦時総動員体制、女性の戦争協力、そして「従軍慰安婦」問題―再審される戦争の記憶を問い、ジェンダーの視点から『想像の共同体=国民国家』の解体を企てる、言説の闘争への大胆な参入。
目次
1 国民国家とジェンダー(序 方法の問題;戦後史のパラダイム・チェンジ;女性史のパラダイム・チェンジ ほか)
2 「従軍慰安婦」問題をめぐって(「三重の犯罪」;「民族の恥」―家父長制パラダイム;朝鮮婦人の「純潔」 ほか)
3 「記憶」の政治学(日本版「歴史修正主義者」たち;ジェンダー史への挑戦;「実証史学」と学問の「客観性・中立性」神話 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Ex libris 毒餃子
8
ナショナリズムに起因する性のあり方に対する論文。国民国家における国民概念の中の女性のあり方について考えさせられる。「従軍慰安婦」問題も問題となった当時の捉え方がわかって良かった。2024/09/22
msykst
5
四年ぶりの再読。一部→戦時下のフェミニストが、(「参加派」「分離派」という)立場に関わらず如何に戦時体制に回収されていったかを見ながら、「女性の国民化」を論じる。二部→慰安婦問題が長らく語られなかった事実を現在進行形の暴力とし、歴史が選択される過程を論じる。三部→歴史構築主義について。リベラル派の連中が実証史観のドツボにはまってるという指摘はナイス。結論はいつもの「脱アイデンティティ」。2009/07/23
Sakana
4
もう20年も前の本だが、色あせない。名著。歴史というのは、「ただひとつの真実」だけを語るものではない。「正史(ナショナルヒストリーなど)」として作られたものの背後にある、不可視され、零れ落ちた「もうひとつの現実」も、またちがう「歴史」としてありうる。あたりまえだけど、うっかりすると忘れてしまいがちな、「無限に再解釈を許す言説の闘争の場」として「出来事」を捉えるということの重要性を、改めて思い知らされた。2018/06/19
FK
4
難しいが何とか読了。「歴史」についての考え方は、共感できる。歴史学者たちはなかなかそれを認められないだろうが。私は歴史を学んだとは言え、「学者・研究者」ではないせいか、むしろ氏の歴史観の方が納得できる。/歴史に「事実fact」も「真実truth」もない、ただ特定の視角からの問題化による再構成された「現実reality」だけがある、という見方(中略)この見方は、歴史学についてもあてはまる。(P.12) 2018/02/01
めじぇど
2
ジェンダーを巡る問題を考えていく時、ジェンダーだけに目を向けていては問題の本質が見えて来ないということがわかった。面白い本。2022/11/23