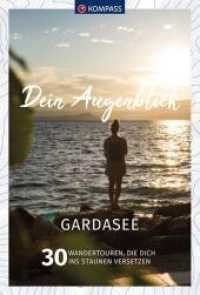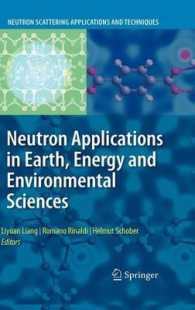内容説明
「ホメオスタシス」「自己組織化」を乗り越える第三世代のシステム論「オートポイエーシス」。システム論の全歴史を通観しつつ、生物学・社会学・心理学・経済学・法学・科学論・歴史学・文学などあらゆる分野の常識を覆すこの革命的システム論を初めて明確に定式化。
目次
1 動的平衡系―第一世代システム
2 自己組織化―第二世代システム
3 オートポイエーシス―第三世代システム
4 オートポイエーシスの展開
終章 システムの日常―カフカ『プロセス(審判)』をめぐって
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Z
11
名著と思う。著者の意図ではないだろうが、「なぜ心あるいは意識を特別なものと思うか、その特異性とは何か」の答えとして読んだ。この本自体は新しいシステム論と呼ばれるオートポイエーシスの解説書だが創始者や応用、発展者の思考の引用ではなく独自の見解を示す。全体に部分の総和以上のものを認めること、この感覚的な表現は有機体(論)に見いだせる。有機体とは開放系=外界と物質代謝、エネルギー代謝を行いながら自己を維持するシステムである。人間体温は外界の変化に対し相対的な一定性を保つ。このようなホメオタシスの機構をこの本では2018/02/18
内島菫
8
オートポイエーシスはいわば隙だらけの理論であり、その分自由度が高く可塑性に富む。隙があるのは、システムを無理に切り取って静止状態にがっちりと固定せずに、作動そのものを問題にしているがための必然なのだろう。又その場合、主体や客体あるいは主観ー客観の未分化というものの作り物っぽさも露呈する。「人間は社会的関係の総体でもなければ、社会的関係の主体的な結節点でもない」という箇所では、ゼーバルト文学にオートポイエーシスを応用して評論してみたくなる誘惑に駆られた。観察システムといたちごっこ的先送りも興味深い課題だ。2015/03/06
Yoshi
4
小難しいことを書いて、煙に巻いた感じの本。結局、定式化ができていないということは、論理的に不明瞭であるということだと思う。 機械論と還元論を区別すべきということには同意。しかし、生物を機械(システム)とモデル化し、目的を不在とする立場は失敗していると思う。自己組織化は、フィードバック概念から目標概念を取り除くことに成功したように見える。一方で、自己組織化(創発)は外部観測者の価値づけが不可欠。観測を取り除くべきというのは自然。しかし、2024/05/09
センケイ (線形)
4
数理系の論文をそれなりに読んできたつもりだったが、その広がる土壌は思っていた以上に広大だったのだ。相互作用であれ外場であれ、さらには座標の取り方であれ、それで良いのだろうか?という懐疑的な見方を余儀なくされる。還元論を支持しようともしまいとも、計算資源の有限さを考えれば、個々のシステムを仮想的に完結したものとして定義する見方には大きな意義がありそうに思う。なお著者のかたは理学出身で、どんな/どのようにモデルが適用可/不可なのか実感されるような距離感にあり、難読ではあったものの安心感が大きかった。2018/04/30
roughfractus02
3
神経システムの実験から「創発」を本質とした閉鎖系システムが抽出され、人間社会の自己言及性(ルーマン)の説明から理論と見做されたオートポイエーシスを、本書は、機械論や生気論では説明不能な自己構成や環境との関係を記述するシステムの3タイプとして歴史的に辿る。環境のゆらぎを修正し自己維持する動的平衡、周辺の条件を有用に自己組織化する動的非平衡、前二者の階層化を撤廃し自己の構成素と作用する自己制作の3システムは、シェリングらオーガニズムの発想に源を置く。これらシステムでは「過去は前からやってくる」(シェリング)。2017/09/24
-
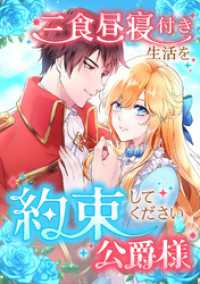
- 電子書籍
- 三食昼寝付き生活を約束してください、公…