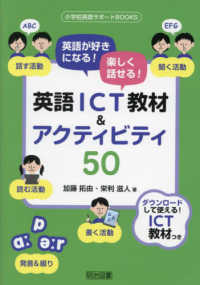内容説明
ヨーロッパはどのように成立したのか。インド・ヨーロッパ語族が、通説よりはるかに古い起源をもつことを立証し、ヨーロッパ人の起源を4000年以上もさかのぼらせ、言語の系譜論に新しい視座を導入して、文明論の展開に画期的な地平を拓いた、問題の書。
目次
序 セイレーンはどんな歌を謡ったか?
第1章 インド・ヨーロッパ祖語をめぐる素描
第2章 考古学から見たインド・ヨーロッパ人
第3章 失われた言語と忘れられた古文書
第4章 原故郷はどこか?
第5章 言語変化の説明モデル
第6章 言語・人口・社会組織―プロセスを通じてのアプローチ
第7章 ヨーロッパにおける初期の言語伝播
第8章 初期インド・イラン語とその起源について
第9章 ケルト人とは誰か?
第10章 誤読された神話群
第11章 考古学とインド・ヨーロッパの起源