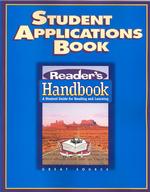出版社内容情報
情報科学技術の発展史に不滅の足跡を遺した数学者ノーバート・ウィーナー。彼が生み出した「サイバネティクス」の理論は、生命と機械の双方を射程に収める統一科学として広範な領域に影響を与えてきた。生成AIが爆発的に普及し第四次人工知能ブームともいわれるいま、その源泉の一つであるとともになおも新たなインスピレーションを掻き立ててやまないウィーナーの思想とそのアクチュアリティに肉薄する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
45
河島茂生:サイバネティクス自体は、1970年代までがピーク(9ページ1段目)。通信工学、制御工学、神経生理学、心理学、社会科学、生態学。ウィーナーの初版は仏、米国でベストセラー(12頁1段目)。杉本舞:低級な労働は、女性や途上国の社会的に立場の弱い人間が低コストで担う(44頁下段)。近藤和敬:創造的活動は、可能態としての計画、デザインの、創造主の意志を作用因とした実現(50頁上段)。現在、欠けているのは、装甲化された人間社会全体の機能像、制御する技術(56頁上段)。2024/09/16
mim42
11
Yuk Huiと丸山、粘菌の斎藤の論文は興味深く読む。三宅ワールドは通常運転。基礎情報学一派のお三方の論文は一神教的教義、読んだ時間を返して欲しい。概念としても対象としても固定していない昨今の大規模言語モデルのようなものを「敵」としてみたて糾弾するやり方は20世紀の左臭い。全体的に学問自体が歴史的対象として強烈すぎるせいか、子孫世代によるナワバリ意識で満ち溢れている。やれドゥルーズがどう言ったなどと参照したがる人は多いが、「機械」という概念と哲学的に向き合っている人がユクぐらいしか見当たらないのはお粗末。2024/08/10
井の中の蛙
9
①サイバネティクスおよびネオ・サイバネティクスの系譜や近年の動向の理解、②ウィーナー自身の人物像の理解、③ユク・ホイの思想の理解の3つを軸として目標にして読み、難しい所やあまり興味を持てなそうな所は飛ばしながら読んだ。サイバネティクスの捉え方が人によって様々であることが初めの河島茂生氏と大黒岳彦氏の対談からすぐに分かった。ユク・ホイの思想に関しては、本人のものより原島大輔氏の「ネオ・サイバネティクスとかなしみの惑星」に分かりやすくまとまっておりよかった。ハイデガー(後期)が読みたくなった。2024/12/05
Haruki
6
サイバネティクスと展開をまとめ的に概観でき良い。大黒-河島対談はさておく。ウィーナーの信号をメッセージ(目的)と雑音の重ね合わせとして捉える通信工学目線と時系列目線(河西)、ベルクソン的器官学(物質の付属物を器官化)としての技術論(宇佐美)、学際の超越論的原理は意味と正当化の可能性の条件の越境(丸山)、情報とは自己が外界への調整行動の際に外界と交換するもの、言語はその固定化(西田)、技術=情報概念、サイバネティクス=二元論の止揚→全体化志向→しかしここに局所性あり=宇宙技芸、技術傾向/事実の違い(ホイ)2024/10/06