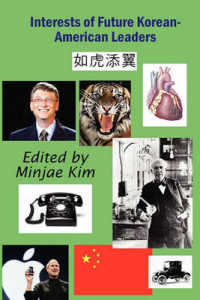出版社内容情報
世界のトップレベルの研究力を目指す大学を10兆円規模のファンドで支援する国際卓越大学法が成立した。政府は最多5~7大学に交付金を配り、低迷する日本の大学の国際競争力の復活を狙う。その成果は未知数であるとともに、大学間の「選択と集中」を強め、格差を広げる懸念もある。コロナ禍で明らかになったことは、大学はただ講義する場ではないということ。そこで教育を受け、研究をし、ただその場にいるだけでも「大学で過ごす時間」に何かを感じ取っている。本特集では、いま一度〈大学は誰のものか〉という問いに立ち返り、課題と可能性を検討する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
45
非常勤講師を思うと、私は高校の方が待遇がいい気もしている。あくまで自分の経験ではあるが。大学という装置、施設にかなり学費が費やされるイメージがある。肝心なのは文化資本を蓄積してあるのだから、その利活用にある。読書会は図書館の真の意義になると思う。大学も独立自尊でお願いしたい。というのは、昨今の朝日新聞朝刊に、図書館の自由を侵しかねない記事が載ったから。大学図書館も、仮に大学が倒産するなら、その文化資本の遺産を国民に還元する方途を探ってほしい。2022/11/05
Ex libris 毒餃子
10
仕事のために。国際卓越研究大学という欺瞞に振り回されております。大学ファンドをJSTが運用してくれますが、利益を還元できるくらいには運用できるか不安です。法人化したのであれば、文部科学省にもっと楯突くなり恫喝するなりしてほしいのであります。2022/11/20