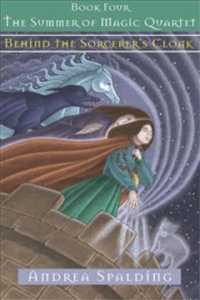内容説明
京都御所、天龍寺、桂離宮、無隣庵、円山公園…文化財保護に長年携わってきた哲学研究者が、平安から現代までの千年をガイド。先入観をぶっ飛ばし、庭の見方を変える旅へ。
目次
序章 時を越えてつながる小学校と平安貴族の住宅
第1章 使わなければ庭ではない―平安時代
第2章 見映え重視のはじまり―平安後期~安土・桃山時代
第3章 百「庭」繚乱―江戸時代
第4章 庭づくりのデモクラシー―近代
第5章 伝統継承の最前線に立つ人々―現代
終章 庭の歴史と現象学
著者等紹介
今江秀史[イマエヒデフミ]
1975年山口県生まれ、京都府京都市育ち。京都造形芸術大学修士課程修了。大阪大学人間科学研究科博士後期課程修了。人間科学博士。現在、京都市役所勤務。専門は、庭の歴史や仕組み・修理・維持管理・職人言葉の研究、現象学的質的研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
85
京都市役所の文化財保護課勤務で、主に庭の文化財の修理と維持管理をする中で、現場で感じたことを元に庭の歴史と現象学を論じている。著者の主張は、明治以降の近代的な学問が「庭園」を分析的に研究しパラダイムを形成してきたことへのアンチテーゼとして、日常生活の状況に応じて機能を変えてきた生き生きとした庭があるということ。平安時代寝殿造りの庭における「大庭」「坪」「屋戸」「島」の4つの分類とそれぞれの用途が歴史的に変遷してきたことを、現在の小学校の校庭や渡り廊下のある中庭、敷地外周の自転車置き場などに見る視点は新鮮⇒2020/08/26
chang_ume
11
庭一般に関する様式重視の通説理解に対して、現象学を背景に生きられた空間(間主観的な実践空間)としての解釈枠組みを提示していく。たしかに日本語で庭といった場合、「庭園」「家庭」「校庭」「前庭」など、意味は非常に多義的で、池泉を中心とした空間限定で庭を理解してよいか、ここは大きな問題提起としてありうると思う。とはいえ「大庭」「坪」「屋戸」「島」の独自四区分の規範として、平安期寝殿造をそこまで重視してよいか違和感はあるし、通説とはやや異なる理解(中世武家の主導性、円山公園の造園主体)には説明がほしかったとも。2021/07/22
chacha
10
偶然図書館の新刊コーナーにあり手にとった。著者は京都市文化財保護課に勤務し、現象学という哲学にのっとった庭の学術研究をされている。日常生活で身近にある庭と建築の関係を系統立てて理解することができます。平安貴族の庭と小学校の庭との例えに庭の四区分の説明は分かりやすい。使わなければ庭ではない。もともとは行事と季節を楽しむもの。我が家の庭にもそのなごりがある。後半部分は少し飛ばし読みになってしまった。2020/09/10
ムカルナス
10
庭の解説をしてくれる本は多々あるが、大方は有名な庭だけをとりあげ、浄土式とか枯山水とか庭を分類し、ナントカ石とかナントカ灯篭とかの説明があるだけ。それはそれで勉強にはなるが庭の見方はやっぱり判らない。かと思うと庭は個人個人が自由に見ていいのですと言う人もいる。本書はそのような庭の見方と一線を画し、庭の成り立ちから説明、当時の人々が庭をどのように使い、どのように愛でていたのか、現在はどの部分が引き継がれ壊されたのかがよく判る。庭の見方の指針が欲しいと思っていた私にはとてもいい本だった。2020/08/09
ポカホンタス
7
一般人にとって、文化財になっているような庭園についてのイメージは、「庭園研究」によって歪められたものでしかなかったということがよくわかった。京都市役所の職員として文化財保護の仕事に就いている著者ならではの、解りやすく、実務的な視点からの歴史分析は痛快。庭は自然と人の暮らしが交錯する場所だったのだ。冒頭、平安貴族の邸宅と現代の小学校の校庭とが並列され、庭の4つの基本区分が提示されるところからすでに圧巻。アカデミックな学術研究というものが持つ欠点を暴く在野研究の醍醐味を味わえる。京都の庭を見に行きたくなった。2020/07/23