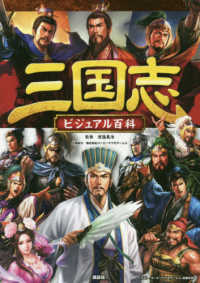内容説明
いつも、読みかけの本を。そばに。本と子どもを愛するすべての人びとの必携書!交わる、出会う、引き出す、ひたらせる、ひらく、交流する、伸ばす。本との取り組み方・付き合い方をサポートし、ひたすら読んで、じっくり考えて、発見する読書教育をデザインする!
目次
1 読書教育の理論(本と「読むこと」と人間―読書教育の存在理由;読書教育の過去と現在)
2 読書教育実践の諸相(本と交わる―読み語り・読み聞かせ;本に出会う―ブックトーク;子どもの読む力を引き出す―読書へのアニマシオン;読むという体験にひたらせる―黙読の時間;読書感想をひらく;感想を交流する;読書能力の発達)
3 読書教育を展開するために(マルチメディア時代の読書とその教育;リテラシーを育てる読書教育の構想;「読書による学習」の開拓へ向けて)
資料編(子どもの読書の現在―全国SLA研究部・調査部「第60回学校読書調査報告」より;読書教育年表)
著者等紹介
山元隆春[ヤマモトタカハル]
1961年、鹿児島県に生まれる。現在、広島大学大学院教育学研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
28
読書教育の目標は、自分の力で読むことのできる読者を育成するところにある。人を自立した読者 にすることがめざすこと(28頁)。ブッククラブの評価基準1~5点(170頁~)。 リテラチャー・サークル:アメリカでの実践。協同的な読書の成立を教室で図ろうとしている(236頁)。 学校ではそうなるだろうが、私は一般市民を対象に考えているので、評価がどうのとか、教育がどう というよりも、一期一会で一人一冊でも構わないので、大学のゼミ並の議論ができるのが理想と思う。 2015/07/19
ng
1
卒論用。2017/04/06