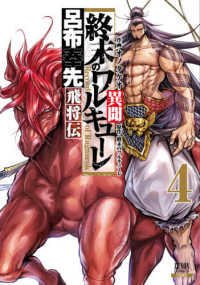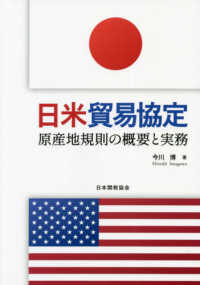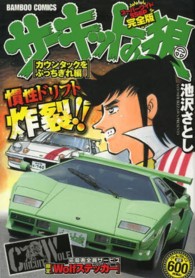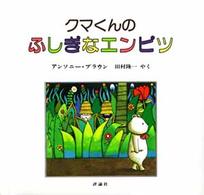内容説明
国語学的方法/国語学の分野/国語史関連年表。日本語の歴史、発音や文法の各分野の現在の水準を明らかにし、これからどのように研究してゆくべきかについて概説する。最新の学説に基づいた教科書。
目次
第1章 資料論
第2章 表記史
第3章 語彙史
第4章 音韻史
第5章 文法史
第6章 敬語史
第7章 文体史
第8章 国語学史
著者等紹介
木田章義[キダアキヨシ]
京都大学大学院文学研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
terve
9
再読。音韻史に関しては本当にお世話になりました。現在は日本語史という名称が多いのですが、私はやはり国語史というべきだと思っています。こういった、世界思想社のシリーズは参考文献を探すのに非常に適しているのでは無いかと思います。2019/08/11
山がち
1
記述がかなりコンパクトに詰め込まれているため、気を抜くとなかなか読めない。しかしながら、過度に専門的というわけでもなく、それでいてある程度の深さを保っているという点でかなり良かった。最初の部分において、国語学というのがそもそも国文学と密接なかかわりを持っているというのが、とかく別物と考えがちな私にとっては重要な言葉だったように思う。また、表記や文体や語彙など、「国語史」という言葉から私自身見落としてしまうような多様な分野について触れられており、言語の多様な側面というのを改めて思い出させてくれたように思う。2013/06/11
御光堂
1
国文学との関係が深く文献学の要素が強かった伝統的な国語学が、言語学のサブジャンルに位置付けられ国文学とのつながりが絶たれ拡散してしまった現状を憂い、あらためて学生に国語学への興味を持ってどのように研究していくべきかを示したという本。「資料」「表記」「語彙」「音韻」「文法」「敬語」「文体」「国語学(研究史)」の各分野の歴史を概説する。「国語史」だが、コンパクトに纏まった「日本語史」として読み易い。文法の項も具体的で分り易い。
サチ
0
日本語史のレポート4本分の参考文献として。ホント使えてありがたい。2020/01/26
サチ
0
日本語史のレポート3本分(再提出用)の参考文献として。ホント使えてありがたい。2020/05/06