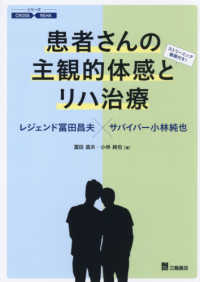- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 哲学・思想
- > 日本の哲学・思想(近代)
内容説明
「作ること」の視点から日本の近代化を再検討する。物を作り人を作る力とはなにか。近代化のかたちの根源に向かって、夏目漱石・柳宗悦・萬鉄五郎・高田保馬・小原國芳・三木清・中井正一・保田與重郎・堀口捨己などを取り上げ、分野を横断しつつ問いかける。
目次
序 作ることの日本近代に寄せて
第1章 深淵をなぞる言葉―夏目漱石『彼岸過迄』のパースペクティヴィズム
第2章 作り手の深層―柳宗悦における神秘と無意識
第3章 「個性」の来源―萬鉄五郎・生ける静物
第4章 近代的知の臨界―高田保馬の利益社会化の法則
第5章 “生命”探求の教育―小原國芳の修身科教授論
第6章 虚無のなかの構想力―三木清・技術哲学の立場
第7章 運動としての「模倣」―中井正一の挑戦
第8章 神話の造形―保田與重郎と知/血の考古学
第9章 「手仕事」の近代―地方の手工芸と一九三〇年代
第10章 一九三〇‐四〇年代の建築における「日本的なもの」と行為概念
著者等紹介
伊藤徹[イトウトオル]
1957年生。京都大学大学院文学研究科博士後期課程・博士(文学)。京都工芸繊維大学大学院教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 妃の秘めごと【タテヨミ】 100話
-
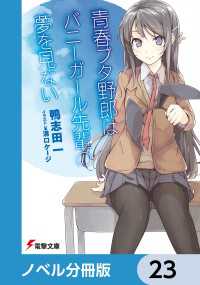
- 電子書籍
- 『青春ブタ野郎』シリーズ【ノベル分冊版…