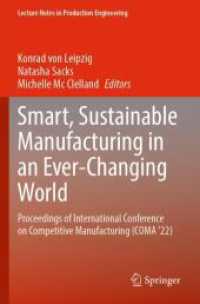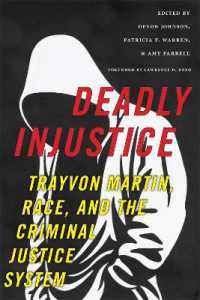内容説明
刑事裁判における「謎解き」はどこまで可能か。三島由紀夫、團藤重光、大森荘蔵、スタンダール、ポー、ホフマン、ラッセル、ウィトゲンシュタイン、ライプニッツ、パース、ローティなど、古今東西の文学と法学、そして哲学の諸領域を横断し、法文化論のパースペクティブのもとに異なるストーリーの申し立てを遊戯的・審理(hearing)的に考察する、試みの書。
目次
1 探偵・推理小説と裁判
2 探偵・推理小説の原型と構造モデル
3 探偵・推理小説、すなわち殺人の制作と証拠法
4 法的推論と事物の本性、あるいはアブダクション
5 法の連鎖と裁判
6 法の解釈とネオ・プラグマティズム
7 普遍法学の夢
著者等紹介
駒城鎮一[コウジョウシンイチ]
1935年富山県に生まれる。1968年大阪大学大学院法学研究科博士課程修了。現在、富山大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゲオルギオ・ハーン
17
推理小説を通してその国の法文化を考察する本かと思いましたが、中身はまったく別物の法哲学の本。推理小説についてはポーと三島由紀夫が何作か書いて飽きたことから遊戯みたいなものだと小馬鹿にするような書き方をしている点で個人的にマイナス評価。トレードオフなどの用語の使い方を間違えており(トレードオフは二律背反じゃないよ先生)、考察も三段論法の体すら成していない読みにくさ。全体の四分の一をライプニッツ語りに使うのは詐欺ではないだろうか。考察の根拠を「〇氏が~と言っていた(から)」でゴリ押しするスタイルなのも残念。2021/03/20
aaaabbbb
1
読了。正確には放棄。推理小説以外の話が多すぎだし、ポストモダン混じりすぎだしで、結局は法文化の本のようだが、法文化やるならもっとまともな本で学びたい。2011/09/14
-

- 電子書籍
- こどものくに 分冊版 11 ジャンプコ…