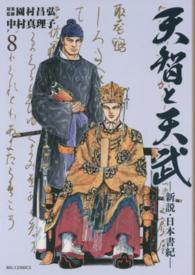出版社内容情報
国をあげての「模倣」と科学の組織化をへて世界一の科学大国へ。先願主義の出発点をなすその過程を詳らかにした、渾身のライフワーク
内容説明
発明と特許の先願主義、コモンズ、世界初の国立研究所、CSRの萌芽カール・ツァイス。国をあげた徹底的・組織的「模倣」による工業化、さらに品質問題をきっかけに、研究所など科学の組織化を通して世界一の「科学大国」へ。その過程を詳らかにし、世界科学史研究にも一石を投じる渾身の意欲作。
目次
19世紀科学と技術の社会史の課題
第1部 模倣と自立(ボイトとプロイセン産業助成協会の設立;模倣―プロイセン王国の技術導入;懸賞問題―自立への模索)
第2部 転回点(新産業・新協会・新科学―ドイツレンガ、陶器、石灰、およびセメント製造協会;リューローと産業助成協会の新展開;品質問題と試験研究所の成立)
第3部 科学大国への道(科学装置万国博覧会と科学器具学、専門協会;企業と研究所―アッベ。ショットとガラス技術研究所、顕微鏡とガラス開発;帝国物理技術研究所の設立)
著者等紹介
宮下晋吉[ミヤシタシンキチ]
1946年生まれ、東京都出身。立命館大学産業社会学部教授。科学技術史、メディア技術史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
志村真幸
0
19世紀後半から、ドイツは国家主導によって科学政策を進め、重工業化に成功したというのが通説だ。本書は、そのあたりを社会史の側面から踏みこむことで、異なった姿を示すことに成功している。 最初にとりあげられるプロイセン産業助成協会が興味深い。官僚と産業界と科学者が結びつくことで、科学の発展が促された道のりが明確にされており、そこからは国家主導ばかりではなかった側面が浮かび上がる。どのような産業分野が当時の重点課題とされ、技術開発が求められていたかが、具体的な事例を扱いながら分析されていくのもおもしろい。2022/07/09
-
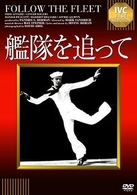
- DVD
- 艦隊を追って