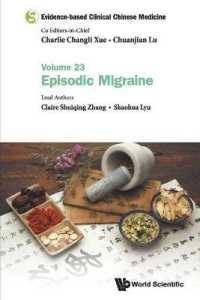内容説明
現代の価値多元的な社会において、なぜスポーツなのか。クラブ、学校、オリンピック、子どもと競技スポーツ、ドーピング、健康、スポーツ科学など具体的なトピックをとりあげつつ、哲学的人間学をベースとして、私たち一人ひとりにとっての、また社会や文化におけるスポーツの意味を問う。
目次
第1部 文化的、社会的そして歴史的文脈におけるスポーツの意味と意味モデル(スポーツと文化との関係について;スポーツの意味と意味モデル)
第2部 スポーツの組織領域と意味領域―クラブ、学校、教育(クラブにおけるスポーツ―新たなスポーツ性と古いクラブ文化;スポーツ教育と学校スポーツ文化―スポーツ授業にとどまらない学校スポーツ;子どもとスポーツ―運動、プレイ、スポーツを通じた子どもの自己経験と世界獲得;オリンピックスポーツの教育学的基礎と倫理的基礎)
第3部 スポーツにおける意味をめぐる議論―応用編(競技スポーツ―意味と責任の問題;子どもの高度競技スポーツ―教育的視点からの分析;競技スポーツの致命的な問題としての成績不正操作と薬物乱用;「新たな」健康スポーツ―フィットネスと安寧と楽しさの間で;スポーツとスポーツ科学)
著者等紹介
グルーペ,オモー[グルーペ,オモー][Grupe,Ommo]
1930年、北ドイツで生まれる。テュービンゲン大学で名誉教授として活発に研究活動を展開。専攻はスポーツ教育学。体育をケルン体育大学で、教育学、哲学、英語学をケルン大学及びミュンスター大学で学ぶ。1958年から1999年に退職するまでテュービンゲン大学に勤務し、その間に同大学をドイツを代表するスポーツ研究の場に発展させる。1957年に博士号(教育学)、1967年に教授資格(哲学)を取得。1976年、フィリップ・ノーエル・ベーカー研究賞。他方、ドイツスポーツ連盟、国立スポーツ科学研究所、オリンピック研究所等で要職を務めるなど、学界のみならずスポーツ界全般を通じて、すでに1960年代からリーダーシップを発揮している。同じテュービンゲン大学で哲学と教育学を担当した、オットー・フリードリッヒ・ボルノーをして、スポーツのことについてはオモー・グルーペに聞いてもらいたいと言わしめたように、彼の力はスポーツ科学界、スポーツ界を超えて広く認められ、影響力をもっている。国際的な学会や研究会などでも、世界を代表するスポーツ研究者として高い評価を得ている
永島惇正[ナガシマアツマサ]
1940年生まれ。日本女子体育大学教授、東京学芸大学名誉教授。スポーツ教育学専攻
岡出美則[オカデヨシノリ]
1957年生まれ。筑波大学大学院人間科学総合研究科助教授。スポーツ教育学専攻
市場俊之[イチバトシユキ]
1957年生まれ。中央大学商学部教授。スポーツ運動学専攻
滝沢文雄[タキザワフミオ]
1951年生まれ。千葉大学教育学部教授。体育哲学専攻
越川茂樹[コシカワシゲキ]
1966年生まれ。岡山大学短期大学部助教授。スポーツ教育学専攻
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。