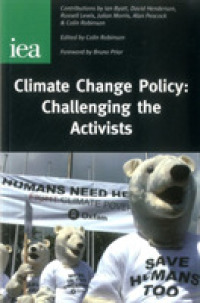内容説明
“女中”というプリズムを通して近・現代日本の家庭生活、とりわけ主婦を中心とした家庭文化を浮き彫りにする。
目次
第1部 “女中”イメージの成立(家庭問題からのアプローチ;“女中”という存在)
第2部 “女中”イメージの展開(家庭問題としての女中;社会問題化する女中;“女中”をめぐる社会事業)
第3部 “女中”イメージの変容(戦後復興期の女中;高度成長期の女中)
“女中”からみた家庭文化・再考
著者等紹介
清水美知子[シミズミチコ]
1958年兵庫県尼崎市に生まれる。1982年津田塾大学学芸学部国際関係学科卒業。甲南大学大学院人文科学研究科応用社会学専攻博士後期課程単位取得。兵庫県家庭問題研究所研究員。関西女学院短期大学専任講師をへて現在、関西国際大学人間学部助教授。専攻は生活社会学・家族コミュニケーション論
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
組織液
13
女中が"家庭"においてどのような意味をもち、イメージを与えていたかがなんとなくわかりました。女中といえば雑にイギリスなどのメイドと同じような存在、日本版メイドなどと考えていましたが、欧米のメイドが近代的な契約による労働者という位置付けだった一方、日本の女中は封建的な主従関係による奉公人、準家族であったという大きな違いがあるようです。戦後の方はちょっとながら読みしちゃいましたね。2022/08/07
海
4
雇った側の家族と暮らし、情のようなもので繋がれた女中と言う制度は、契約で結ばれた欧米のそれとは違いこの国独特のものだったらしい。それが雇われる側の待遇改善要求や、家電製品の進歩、居住スタイルの変化などによって崩れていき、やがて「女中」と言う言葉が死語になるまでの変遷がわかりやすく書かれている。2012/01/26
-

- 和書
- 幕末政治思想史研究