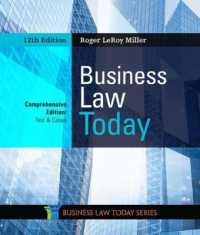内容説明
戦後の「平和」な日本社会にあらわれる「戦争」を社会学の視座から問い直すユニークな論集。
目次
戦後「平和」のなかの「戦争」
戦没者の手記分析についての一考察―森岡清美『決死の世代と遺書』をめぐって
鎮められない戦争の記憶
被爆地広島における寺院の役割
実業家文化の戦前・戦後
公衆衛生の危機管理―保健所の変遷
戦後男の子文化のなかの「戦争」
一九六〇年代少年週刊誌における「戦争」―「少年マガジン」の事例
自衛隊PKOの社会学―国際貢献任務拡大のゆくえと派遣ストレス
「満洲国」の現実と理想―崩壊時の体験
「満州移民」の問いかけるもの
統一ドイツのナショナル・アインデンティティ形成―ホロコースト慰霊碑論争にみる戦争の記憶
著者等紹介
中久郎[ナカヒサオ]
1927年、京都に生まれる。京都大学大学院博士課程修了。文学博士。大谷大学、京都大学、龍谷大学教授を経て、現在は、京都大学名誉教授、愛知新城大谷大学学長。専攻は、社会学理論、社会学史、社会病理学
高橋三郎[タカハシサブロウ]
現職は広島国際学院大学現代社会学部教授
青木康容[アオキヤスヒロ]
現職は仏教大学社会学部教授
新田光子[ニッタミツコ]
現職は龍谷大学社会学部教授
永谷健[ナガタニケン]
現職は名古屋工業大学助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Toska
15
戦後日本がどのように戦争を引きずったか、また引きずらなかったかという問題を基調とする、研究者11人の論集。個々のテーマは多様で、被爆後の広島における真宗寺院の再建(新田光子)や、PKOに参加した自衛隊員のモチベーション(河野仁)など様々な方向に広がっている。高橋三郎の論考によれば、戦没者の手記を読み解くには行間を読む力が不可欠だが、この点で当時の「常識」を知る同時代人に勝る者はいないという。つまり、研究者の世代が進むにつれて読解が難しくなるわけで、これは深刻な指摘と思う。2024/07/11