内容説明
「異文化の学」としての文化人類学の方法的な特質を損なわずに、しかも自らが生まれ育った文化そのものへと視線を折り返す試み。日本文化そのものの斬新で且つ深い理解に役立つ学問へと文化人類学を回転させようとする構想に資する論考を編んだ。
目次
第1部 日本文化の論理発見(鷹揚な河童と謹厳なハイエナ―超越的な時間とそれに抗する時間のエージェントたち;「オムスビの力」と象徴―象徴的日本民俗論のために;「斜め嫌いの日本文化」再考)
第2部 飛騨高山の文化人類学の試み(「味噌買橋」の渡り方―民俗学と歴史学はいかにして出合えるのか;ヒノキからオークへ―日本文化の「斜め嫌い」超克と飛騨高山の経験)
第3部 異文化としての自文化の理解(幼稚園のトーテミズム―幼い娘のしてくれた構造人類学講義;笑い殺す神の論理―笑いの「反記号」論の基底について)
著者等紹介
小馬徹[コンマトオル]
1948年、富山県高岡市に生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。大分大学助教授、神奈川大学外国学部教授を経て、現在神奈川大学人間科学部教授。文化人類学・社会人類学専攻。1979年以来、ケニアでキプシギス人を中心とするカレンジン群の長期参与観察調査を37度実施、現在も継続中。『川の記憶』“田主丸町誌第1巻”(共著、第51回毎日出版文化賞・第56回西日本文化賞受賞)1996、『日向写真帖―家族の数だけ歴史がある』“日向市史別編”(共著、第13回宮崎日々出版文化賞受賞)2002をはじめ、日本の民俗研究や地方史など、人類学以外の諸領域の著述も多数執筆(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
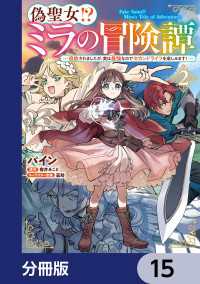
- 電子書籍
- 偽聖女!? ミラの冒険譚 ~追放されま…
-
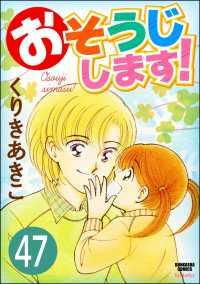
- 電子書籍
- おそうじします!(分冊版) 【第47話】





