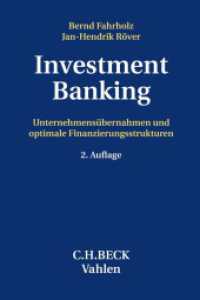内容説明
日本刀が実体としても観念としても遠くなった今、「竹刀は日本刀の代用」と考えるのではなく、日本人の伝統的な「動作原理」を基盤に、まったく新しい剣道技術論を構築する。
目次
第1章 日本刀代用論とは
第2章 日本刀の消失
第3章 「50年理念」とその矛盾
第4章 様式的結果性技術論
第5章 日本人の身体特性と動作
第6章 歩き方にみる「動作原理」
第7章 「単え身」による剣道
著者等紹介
木寺英史[キデラエイシ]
九州共立大学スポーツ学部スポーツ学科准教授。昭和33年熊本県生まれ、剣道教士七段。筑波大学卒業後、高等専門学校教員を務めながら、剣道の技術の研究をきっかけとして他分野の研究者やスポーツ選手との交流を深めつつ「常歩(なみあし)」理論を構築。平成16年に著した『本当のナンバ常歩』(スキージャーナル)が大反響を呼び、以後剣道界に留まらず、スポーツや身体操作全般にわたって精力的な著作活動、講演、コーチングなどの活動を続けている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
鉄刀木
0
序盤、剣道は刀法のしがらみ故に競技として歪であり、そこから離れて剣道は竹刀を使う競技として独自の理論の積み上げを行うべき、という風に読めたので、そこから多くの剣道家が研鑽した竹刀の運用理論が開陳されるのかと楽しみにしていた。 しかし最終的には、ある一つの理論が歩き方に触れていることから歩行の話になり、それが著者の唱えている歩法へ誘導するかたちになっている、という印象を持ってしまったのが残念だった。2015/10/26
Arisaka
0
(28)『日本刀を超えて』…武道は「礼に始まり礼に終わる」とは聞いたが、まさか「一撃でしとめ、余計な苦しみを与えないことが最低限の『礼儀』である」とする「生死観」すら求めらるとは知らなかった。奥深い武道の精神を学べる一冊!2015/05/10
Hiroyuki Asaji
0
現代剣道は、竹刀が日本刀の代用という考え方と運動様式の変化により、矛盾が出ていると指摘しています。それを脱するために竹刀の日本刀代用論から、日本人の伝統的な身体操作を基準に変えることで、剣道らしさを維持する事を提唱しています。興味深かったのは、かつての日本人は職業ごとに特徴的な身体の遣い方をしていた事。多様な身体の遣い方があったようです。日常的な身体の遣い方は史料に残る事がないので、かつての日本人の動きは想像するしかありませんが、そのような伝統的な動きの中に貴重な文化が詰まっていたのかも知れませんね。2014/06/08