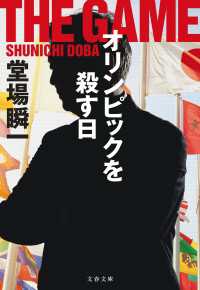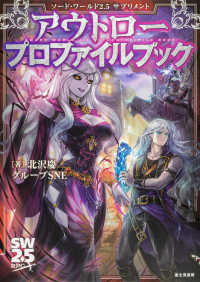内容説明
“マネジメント”は“管理・統制”ではなく、目標を達成するために作業方法を変える努力のことである。激励や叱責に代わる科学的な行動原則を解明した書の新訂版。
目次
マネジメントの原則
企業文化
行動の意味
ウィークリー・マネジメント
マネジメントの手法
マネジメントの着眼点
マネジメントの進め方
不振の克服策(体質手術の進め方)
チェーンストアのシステムづくりと組織的運営
マニュアルの意味とつくり方
アウトプット・マネジメント
あるべき経営効率
著者等紹介
渥美俊一[アツミシュンイチ]
1926年、三重県に生まれる。官立第一高等学校文科を経て、1952年、東京大学法学部卒業。読売新聞社経営技術担当主任記者として「商店のページ」を一人で編集・執筆。1962年から、チェーンストア経営研究団体ペガサスクラブを主宰。現在、加盟六〇一社で、わが国唯一のチェーンストア経営専門コンサルティング機関である日本リテイリングセンター・チーフ・コンサルタント。ほかに日本チェーンストア協会相談役(元同初代事務局長)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。