内容説明
社会福祉、その歴史研究の積み重ねが、その未来を切り開く。少子高齢化、財政問題、日本経済の弱体化のなかで社会福祉をどのように創っていくのか。重層的、多様な性格をもつ社会福祉。社会福祉史研究の実績ある著者が、その発展過程を「歴史的思考」するなかで読み解いていく。
目次
1 社会福祉史をめぐる研究の歩み(社会福祉施設史研究の動向;石井十次の「信仰」について―キリスト教史・キリスト教社会福祉史研究での扱いをめぐって;社会福祉史研究における渋沢栄一)
2 キリスト教による地域実践の展開(一九三〇年代のキリスト教による農村社会事業の発展;東京におけるキリスト教セツルメント―戦時下の困難から戦後の再建を通して;有隣園によるセツルメント活動の歴史的意義)
3 キリスト教社会事業の財源をめぐって(鉄道の発展と岡山孤児院;キリスト教社会事業の展開における財源問題 ほか)
4 ハンセン病問題と向き合う(ハンセン病問題をめぐる責任について;渋沢栄一とハンセン病との関係)
5 地域社会福祉史の探求(地域社会福祉史研究の意義と課題;山口県社会事業と女性 ほか)
著者等紹介
杉山博昭[スギヤマヒロアキ]
1962年生。日本福祉大学大学院修士課程修了。特別養護老人ホーム、障害者作業所、宇部短期大学、長崎純心大学を経て、2008年よりノートルダム清心女子大学人間生活学部教授。博士(学術・福祉)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
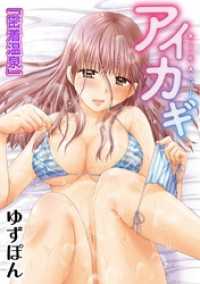
- 電子書籍
- アイカギ【単話】(53) モバMAN
-

- 電子書籍
- サギ恋~タイパ詐欺女とプチロマンス詐欺…
-

- 電子書籍
- 盛岡タウン情報誌月刊アキュート 202…
-
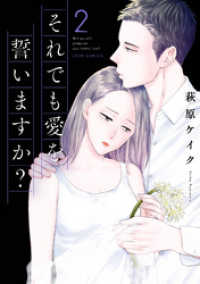
- 電子書籍
- それでも愛を誓いますか? 分冊版 8 …
-
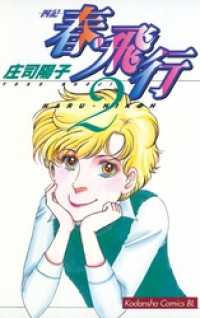
- 電子書籍
- 春・飛行(2)



