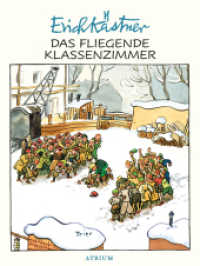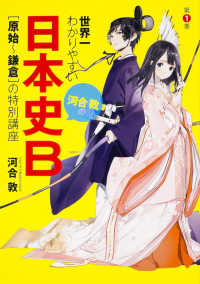内容説明
私たちの周りには多くの境界がある。そのどれもが何かを基準として分類され、創られてきたものだが、いったいその基準とは何か。本書は日本の地域社会をフィールドとして基地、観光、漁業慣行、限界集落、市町村合併をキーワードに、人々がどのような基準で境界を認識し、創ってきたかを分析したものである。
目次
第1章 沖縄の基地周辺共同体と文化継承に関する“境界”領域の人類学的考察(課題と目的;強制移転村―読谷村楚辺の事例から ほか)
第2章 境界に生まれる文化―周防大島における文化の真正性と言説の生成(宮本常一の観光論;分析的視座 ほか)
第3章 境界/越境と「人の移動」―周防大島の漁協と漁業慣行(山口県東和町の沿革と概況;周防大島の漁協と漁業 ほか)
第4章 奄美民俗社会における地域社会維持の境界について―鹿児島県大島郡大和村の事例から(離島(奄美群島)における過疎化、高齢化の特徴
大和村の概況 ほか)
第5章 市町村合併をめぐる境界性の問題―山形県金山町・鹿児島県南さつま市坊津町の事例から(平成の市町村合併;山形県金山町の合併をめぐる問題 ほか)
著者等紹介
大胡修[オオゴオサム]
1945年生まれ。明治大学政治経済学部定年退職(2016年)。同大学名誉教授
山内健治[ヤマウチケンジ]
1954年生まれ。明治大学政治経済学部教授
岡庭義行[オカニワヨシユキ]
1967年生まれ。帯広大谷短期大学地域教養学部教授
林研三[ハヤシケンゾウ]
1951年生まれ。札幌大学法学部教授
石川雅信[イシカワマサノブ]
1954年生まれ。明治大学政治経済学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- マイ・フェア・レディ