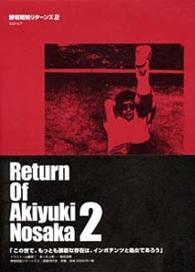内容説明
マルクス哲学の理論的核心たる疎外論を縦横に論じ、現代的適用を模索するなかで廣松らの俗流理解に徹底的な批判を加え、マルクスそのものの復権を図る!!
目次
第1部 哲学と疎外論(マルクスの哲学;マルクス疎外論の可能性と限界;疎外論と実践的唯物論)
第2部 疎外と物象化(疎外は「人間生活の永遠的自然条件」ではない;物象化と物神崇拝の関係;マルクスの物象化論と廣松の物象化論)
第3部 認識と規範(反映論の意義;マルクスの分配的正義論;トリツキーの道徳論)
第4部 マルクスの正しい理解のために(生産力概念についての一提言;曲解されたマルクス;神話のマルクスと現実のマルクス)
著者等紹介
田上孝一[タガミコウイチ]
1967年東京生まれ。1989年法政大学文学部哲学科卒業。1991年立正大学大学院文学研究科哲学専攻修士課程修了。2000年博士(文学)(立正大学)。現在、立正大学非常勤講師。専攻は哲学・倫理学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
しお
2
本書はまず、マルクスの疎外概念を(円熟期まで一貫するものとして)事物が規範から外れるという様態として規範論的に規定することから始める。実存論的な主観主義の術語としてではなく、価値判断の倫理学的なカテゴリとして田上は解釈するのだ。このもとで、『資本論』に通底する「物象化」は、認識論的にではなく、PersonのSache化としてこれまた規範論的、存在論的に定立される。これこそが、「断絶」説に基づく廣松による「物象化論」の批判や、マルクスそれ自体の哲学史的な位置付けの発見のために、田上が置いた賭金に他ならない。2021/02/19
メイキー
2
5時間程で読了。漠然としていた疎外-物象-物神崇拝の関係性並びにマルクスの疎外論の徹底性を理解するのに充分なボリュームを呈してくれた本であった。個人的には廣松、今村というビックネームの二者を、字義通り快刀乱麻を断ってくれた。著書の内容ではないが、アルチュセールと廣松渉についての私の細やかな疑問についてどちらもスターリン主義の亜流であると著者自身が回答して下さったこと、またその理解のための橋渡しとしてこの著書を紹介して下さったことも感謝の念でいっぱいである。2013/09/17
トックン
1
倫理学者によるマルクス解釈。廣松による解釈ではマルクスの後期には克服されたとする<疎外>というタームを初期から一貫して重要なものとして田上は再解釈する。その理由は<疎外>とは規範的概念であるからだ。そしてPersonalな疎外の対概念である「物象化」を誤訳だとして、モノding感を強く押し出すため「物件化」を提唱する。スターリンや廣松により解釈されたマルクスではなく、真のマルクス像を描こうとするのは良いが、コップの中の嵐では?疎外の克服は永久に終わりそうにない2017/07/09