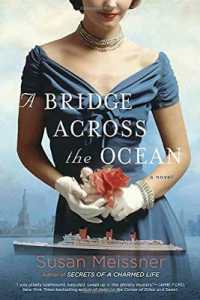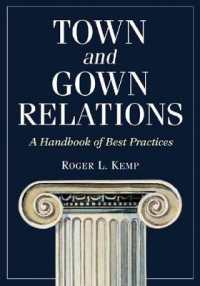出版社内容情報
「うちの親はまだ元気だから、相続のことを話すのはもう少し先でいい」
「うちは、兄弟仲がいいから大丈夫」
「そんなに財産があるわけではないから、うちは大丈夫」
そんなふうに思っていませんか?
相続の専門家集団である私たちが相続の現場で何度も目にしてきたのは、「元気なうちに話しておけばよかった」という後悔です。
親御さんが突然倒れたり、認知症を発症されたりしたことで、意思確認が難しくなり、相続対策の選択肢が限られてしまうケースは少なくありません。
だ
【目次】
はじめに――相続の「準備をする」という優しさ
「まだ早い」は「もう遅い」かもしれません
広島に根ざした専門家たちの視点から
節税よりも大切なこと
第一章 いま考えたい、親の相続と家族のこれから(永戸康弘、大原清丈)
50代で相続を意識し始める理由
親の介護、認知症、空き家──暮らしの変化が教えてくれること
相続は「最後の家族会議」ではなく、「これからの人生&生活設計」
相続でよくある""後悔""と、その背景
――「あと1年早
内容説明
資産管理、事業承継、未来設計。相続の不安を“安心”に変えるには、50代からの相続準備が肝要。「うちは大丈夫」と思った人が、相続では一番危ない。家族と資産を次世代につなぐ相続のルールとは。
目次
第1章 いま考えたい、親の相続と家族のこれから
第2章 家族が納得できる相続のためにできること
第3章 資産を「守り」「活かす」
第4章 状況が複雑なときに考えるべきこと
第5章 「何から始めればいいか」が分かる基礎知識
第6章 地域に根差した専門家たちの取り組み
著者等紹介
藤本律夫[フジモトリツオ]
ライフグループ代表。広島県広島市出身。広島を拠点に、相続不動産と家族信託を専門とするコンサルタントとして、多くの相談・実務を手がける。行政書士・不動産・税務の各分野をグループ内で有機的に連携し、相続手続きから資産承継、不動産活用、税務対策までを一貫してサポート。複雑な家族・資産状況にも丁寧に寄り添い、円満な承継と資産の最適化を実現している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Go Extreme