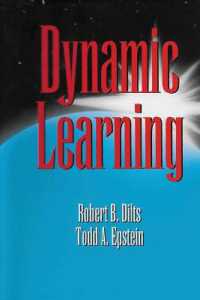内容説明
教育問題を自明視するのではなく、少し日常から引いた視点でとらえ直して、新しい教育の可能性を問いかける。関係者待望の書。
目次
第1章 教育界の怪しい言葉(教育の「マジック・ワード」;教育を語る言葉はなぜ修飾過剰になるのか? ほか)
第2章 迷走する教育改革(なぜ改革が良い結果をもたらさないのか;教育論議は広く、深い思考で ほか)
第3章 子ども・学校・社会(「親s」「家庭s」の発想;教員と親との関係を組み立て直す最良の道は? ほか)
第4章 教育はどう変わるのか(教育改革について考えてみる;社会モデルと教育改革案)
著者等紹介
広田照幸[ヒロタテルユキ]
日本大学文理学部教授。1959年広島県生まれ。東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学。南山大学文学部講師・助教授、東京大学大学院教育学研究科助教授・教授を経て、2006年より現職。内閣府・子ども・若者育成支援に関するワーキングチーム委員等を勤める。専門は教育社会学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たろーたん
2
教育議論の問題を指摘した本。著者は「教育のマジックワード」として三つを上げる。一つ目は「便利だが怪しい言葉」、例えば「生きる力」等だ。中身があるようでなく、どうとでも解釈できるもの。他にも「個性」とか。「個性ってなんだ?」とか「個性に応じて」というと具体的によく分からなくなる。子供に「あなたの個性に応じた教育をします」と言うと「僕の個性って何ですか?」って返されるだろう。さらに子供が「どうしてそれが僕の個性なんですか?本当にそうですか?」と質問をされたどうするのだろう。(続)2025/02/12
nako*beary
2
着地点はない。でも、「生きる力」とか「徳育」とか、ぱっと聞くと納得してしまったり、なにも言えなくなったりするマジックワードが教育を題材にした議論には存在するのだ!という主張はありがたい。これからどうなる?じゃなくてどうする?と問うことの重要性。2014/11/09
ほりほり
1
かなりくだけた文体で読みやすく、昨今の教育論議がどのようにおこなわれて来たのか大まかに掴むには最適。冗談がたくさん散りばめられているのだが、いやー最近の教育論議は冗談みたいなことを大真面目にやっていますからね、笑うに笑えないよなぁ…と思う箇所もしばしば。「これからの教育はどうなっていくんでしょうね…」などと、教育の未来は占うものではない。「これからどのようにするか」をみんなで考えましょう、という著者のメッセージはしっかりと受け止めなければと思った。2015/04/28
msy3a
1
抜粋 保守勢力の社会論 上に立つ者が権威や威厳を持ち、下で指示や命令に従う者がその権威を受け入れているような状態を好ましいと考えます。だから、あらゆるメンバーが対等な関係で社会や集団をつくる、といったあり方は「行き過ぎた平等」と考えます。かっちりした上下関係が好きなんですね。(略) 「共同体」も大好きです。「共同体」としての一体感を持たせることができれば、金持ちも貧乏人も、男も女も「(較差や差別や抑圧があったとしても)みんな一心同体だ」というふうに、不平や不満を抑えこんでしまうことができます。2014/04/26
Takanobu Y
1
良書。 「今の学校の先生に強い不信感を持っています。・・・その一方で『あるべき教師像』については、おそろしいほどの期待をしています。」 「市場原理でサバイバル競争させたら、個々の先生が『やる気』を出してすべての理想が実現する、と思っています」 教育の素人による、市場原理導入が、現在の混乱を引き起こしています。2012/07/27