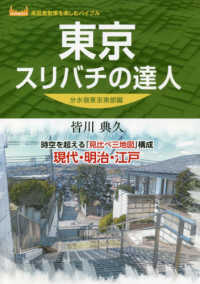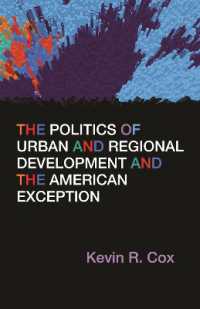出版社内容情報
超高齢者の終末期に過剰な医療的措置を施されたり、尊厳死という死の自己決定を強いられたりすることなく、いかにして自然死(老衰死)を迎えることができるか。実父の最期の6日間の介護記録から、日常的なケア以外は何もせずに看取る作法を考える。
内容説明
医療的な論理ではなく介護的な実践による、尊厳ある生のなかでの逝き方とは?超高齢者の終末期に過剰な医療的措置を施されたり、尊厳死という名の死の自己決定を強いられたりすることなく、いかに穏やかな自然死(老衰死)を迎えることができるのか。実父の最期の6日間の介護記録とその後のグループホームでのインタビューから、終末期のとくに疾患のない高齢者に対する「日常的なケア以外のことは何もせずに看取る」作法を考える。
目次
第1章 “尊厳ある生”のなかでの看取りとは?
第2章 “医療行為をしない人の死”はどのように訪れるのか?
第3章 介護スタッフの実践から見えてくる“本人の意思”
第4章 「最期の入浴ケア」が残したもの
第5章 “介護と医療のより良き連携”のゼロ地点から
第6章 訪問看護師―その役割の多様性と柔軟性をめぐって
第7章 “そのとき”は、いつ訪れるかわからない?!
第8章 “交響する看取り”のなかで
第9章 「生かす介護」から「もう少し楽な介護へ!」
著者等紹介
三浦耕吉郎[ミウラコウキチロウ]
関西学院大学教授。専門は、生活史、差別問題、環境社会学、質的調査法(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひつまぶし
5
タイトル通りの内容。自然死を可能とするための条件、施設職員の実践が、著者自身の体験と聞き取り、ケース記録から考察される。しかし、著者が一番興味があるのはそういった理解をする自分自身なのだろうなと思う。難しい問題、複雑な現象に対して自分の中でどのように理解が固まっていくか、そしてその理解を可能にした枠組みたる自己の輪郭をつかもうとしている。それが溢れ出している一方で、著者はそのことを自覚しきれていないのだと思う。個別のテーマに関心を抱く読者にとっては著者の気づきの戸惑いや理解の驚きそのものは必須ではない。2025/07/03
takao
0
ふむ2025/03/18
-

- 電子書籍
- THE QUEEN~稀代の霊后~【タテ…