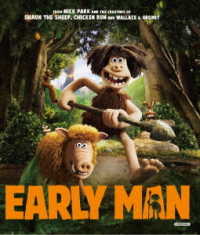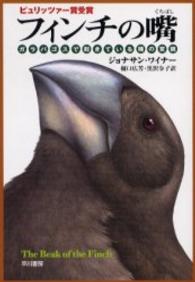内容説明
「精神医学」「心理学」「心の哲学」の三つの視点から、精神科臨床や心理臨床を含む心の臨床全般を哲学的に検討。実践に臨む視野が大きく広がる。
目次
第1部 精神医学(精神医学の「二つの心」;精神療法家は人の人生観にどこまで踏み込めるのか;精神科医はどのようにして心を理解するか?―了解・シミュレーション・共感;自閉スペクトラム症への医療介入における妥当性の問題:試論;「クイ・ボノ?」(“Cui bono?”)―精神医学は「あなたのためを思えばこそ」なのか?)
第2部 心理学(心理教育の心類学―予防・布教・マーケティング;ナラティヴ・アプローチによる心理臨床―人々の「声」を取り戻す実践;比較心理療法論―認識論と心の哲学からの考察;性格心理学をめぐるいくつかの問題)
第3部 心の哲学(精神医学の多元性と科学性;感情労働と心の病;言語を持たない動物は精神疾患のモデルになるのか?―精神疾患の動物モデルと精神医学史における発見;薬物依存症者に対する適切な非難のあり方―非難の関係性説に基づく依存行動への対応;精神障害(精神疾患)とは何か)
著者等紹介
榊原英輔[サカキバラエイスケ]
東京大学医学部医学科卒業。精神科医、臨床心理士、公認心理師。大学在学中に東京大学教養学部科学史・科学哲学科で学ぶ。現在は東京大学医学部附属病院精神神経科助教
田所重紀[タドコロシゲノリ]
東京大学文学部、千葉大学医学部卒業。千葉大学大学院医学薬学府博士課程修了、東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。精神科専門医、臨床心理士、公認心理師。現在は室蘭工業大学保健管理センター教授
東畑開人[トウハタカイト]
京都大学教育学部卒業。京都大学大学院教育学研究科博士後期課程修了。博士(教育学)、臨床心理士。現在は十文字学園女子大学人間生活学部人間発達心理学科准教授。白金高輪カウンセリングルーム開業
鈴木貴之[スズキタカユキ]
東京大学文学部卒業。東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。博士(学術)。現在は東京大学大学院総合文化研究科准教授。専門は心の哲学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひろか
ゆうみい
ぼっせぃー
てんたかく
Go Extreme