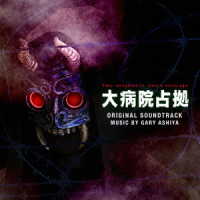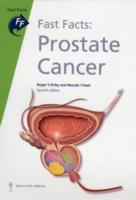内容説明
世界中の子どもたち、若者、そして企業人が取り組み始めた!今の自分を超えて、ヴィゴツキーの「頭一つの背伸び」をもたらす、協働で遊ぶ=プレイする=パフォーマンスすることの力。新しい、「発達する」環境を生み出す生成の心理学への招待。
目次
第1章 方法とマルクス
第2章 ヴィゴツキーとセラピー―情動発達の領域を作り出す
第3章 教室で―パフォーマンスの学習、学習のためのパフォーマンス
第4章 学校の外で―創造的模倣と他者の受け入れ
第5章 仕事場で―自分を見つめる
第6章 変化する関係性
著者等紹介
ホルツマン,ロイス[ホルツマン,ロイス] [Holzman,Lois]
1977年コロンビア大学大学院修了、Ph.D(発達心理学)。ニューヨーク州立大学エンパイアステートカレッジ准教授を経て(1979年~1996年)、現在、グループと短期心理療法のためのイーストサイド・インスティチュート所長。ヴィゴツキーやソーシャルセラピーについての多くの単著、共著がある
茂呂雄二[モロユウジ]
1981年筑波大学大学院博士課程心理学研究科単位取得中退。博士(教育学)(2000年東京大学)。国立国語研究所言語教育研究部主任研究官を経て、筑波大学人間系心理学域教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ブルーハート
2
ヴィゴツキー理論をどのように実践的にどのように取り込んでいけばよいか、一つの、しかし大切なヒントがシンプルに述べられていて良書。2016/12/22
松村 英治
1
もう一度読まないと理解しきれていないが…遊びの中では、その遊びのやり方を知らなくても、背伸びをしながら即興的にパフォーマンスし、日常生活では不可能なことも、頭一つ抜け出たもののように行為する。だからそういう学習を、学校を始めとする教育の中で実現していかないといけない。即興、創造、遊び、創造的模倣、zpd。2016/06/12
Miki Kusunose
1
前半難しくてうーーー、と悩みましたが後半の学校での話からは分かりやすくて一気によめました。インプロな研修、受けてみたいな。2016/01/21
うみ
0
最初のあたりのセラピー云々のくだりはどうにもよくわかんなかったけども,教室の中の話になったあたりからおもしろくなってきた。後半は,インプロやってる方にはもっと腑に落ちたり,疑問がわいてきたりするんだろうなぁと思う。私は,「あ,そろそろインプロまたやってみたいな」って気持ちになったのだけど。当初期待したヴィゴツキーの入門書…ではなかったのだな。でもいいの。周辺から攻めてく。2015/01/21
akagiteaching
0
いやー,面白い。「生成の心理学」というより「変身の心理学」。違う自分になっていくプロセスを発達ととらえる。そのプロセスを握る鍵は,即興的パフォーマンス。なるほど。2014/10/15
-
- 洋書
- Kickoff!