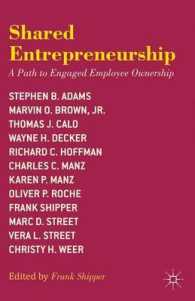内容説明
認識の知から、臨床・実践の知へ。損なわれた身体や環境はいかに創発・再生するか?従来の視覚的・言語的な西欧の知では解けなかった喫緊の難問に、行為の知を掲げるオートポイエーシスの第一人者が、自らの大病体験をへて挑む。セラピー、リハビリ、トレーニングなどの実践の現場でも読まれるべき知的冒険の書。
目次
序章 システムの創発と再生へ―気づきと触覚発達と能力の形成
第1章 認知行為的世界(感じ取る自己と世界;認知行為のカテゴリー;認知行為と現象学)
第2章 システムの発達(発達論の難題;発達のモデル変更;発達のさなかの謎)
第3章 記憶システム(記憶という課題;記憶という構想;情動の記憶;記憶の補遺)
第4章 動作システム(動作の多様化;動作の組織化;意識の行為;動作の言語)
第5章 能力の形成とオートポイエーシス(経験の可動域;人間再生のシステム;オートポイエーシスという経験)
終章 希望―ヘルダーリンの運命
著者等紹介
河本英夫[カワモトヒデオ]
1953年、鳥取県生まれ。1982年、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。1996年、東洋大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
2
システム論ではなくシステムを記述する著者は記述不能な複合運動系(第四領域)に出会った(『システム現象学』)。さらに二度の手術を経た後の本書で著者はシステムの構成素自体を注視する。記述する側は治療過程へ、記述される側は損傷した身体の再生過程へ、記述自体は両者の継続から現象する構成素の産出過程へと接近する。位相空間からの産出過程は、線形性を前提した言語による理解では先に進まない。第四領域(感覚、感情、身体行為)の形成運動は非線形的だからだ。それゆえ読者も、理解に留まらない読書過程を産出するように作動を続ける。2017/09/28
Soshi Mori
1
長くかかったが、読了。ものすごくエネルギーを要したが、充実感は半端ない。 河本先生の文章は読む度に少しずつ開けてくる。経験として確実に身体に染み渡ってくる。書かれていることが実践できるのは恐らくまだまだ先。ただ少しずつ展開していっているのだろうと思う。2014/05/05
-

- 電子書籍
- 朝起きたら探索者になっていたのでダンジ…
-

- DVD
- 遠い国