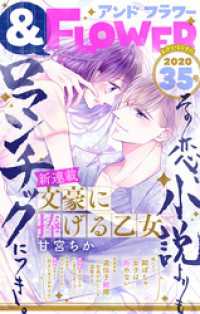内容説明
赤ちゃんや幼児の、驚くべき認知能力をつぎつぎと明らかにしている心理学―しかし、どのようにしてわかったのか?心理学の実験的な方法の醍醐味を味わいながら、乳幼児の世界を探険する心理学ツアーへの招待。
目次
1章 実験から乳幼児の心を探る
2章 乳児の有能さ
3章 乳幼児の記憶
4章 生き物をどう理解しているか
5章 心をどう理解しているか
6章 物の世界をどう理解しているか
7章 自分をどう理解しているか
著者等紹介
外山紀子[トヤマノリコ]
東京工業大学総合理工学研究科博士課程修了。現在、津田塾大学教授。博士(学術)。主な研究分野は、認知発達
中島伸子[ナカシマノブコ]
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科博士課程修了。現在、新潟大学准教授。博士(人文科学)。主な研究分野は、認知発達(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Isamash
15
外山紀子津田塾大教授及び中島信子新潟大准教授の2013年著作。乳幼児の有能さ、乳幼児の記憶、生き物・心・物・自分をどう理解しているかに関する実験心理学のこれまでの知見をかなり網羅的に紹介していて興味深く読めた。最後の章では幼児の楽天主義を記し失敗を経験させることの意義を述べている。学問的論争があるところや実験方法により相反する様な結果が出てること、研究の流行(心の理論研究がブームらしい)にも触れられ、研究の臨場感がある良書と感じた。他人がどう考えているか(誤信念)を何と2歳児が一部既に理解しているらしい。2022/01/19
くろまによん
6
乳幼児にまつわるさまざまな研究や実験が記されている。特に面白かったのは、6ヵ月のときの記憶を2歳になっても覚えているという研究結果。これは意外だった。あと飲食物の汚染の概念についての実験ね。3-6歳児の前で水の入ったコップにゴキブリ(のおもちゃだろうと思う)などの汚染源を浸し、それを取り除いた上で、「飲む?」という問いに多くの子どもが「うん」と答えた。これをもって汚染は未発達とされていたが、後の時代に質問を変えて「他の子がこれを飲んだら具合が悪くなるかどうか」を判断させたところ、3歳児の80%が――2016/06/28
yurari
4
大人が思っている以上に乳幼児は物事を分かっているようだ。同じ質問を繰り返すとそれが子供にとって社会的圧力となり、子供の証言を誘導しがちになるという話には驚いた。 また、様々な角度から経験した出来事について質問をして内容を豊かにすると、子供は多くを語るという話にもなるほどと思った。/言語は経験した出来事を意味のある一つの物語としてまとめたり、思い出すときの手がかりとして機能するといった効果があると考えられる。/5歳までには多くの子供が老化は身体内部から引き起こされる現象であることに気付くようになる/2023/11/08
じろ
2
★★★ 乳児がいる間にこういうのめちゃよんだろと思って借りた本。面白かったけど乳児に対する実験はちょっと方法に疑問があるな…乳児にとっての注視って大人と一緒か?2018/11/04
いし
1
本書を読む前は、乳幼児が見ている世界をどうやって把握するのだろうと思っていたが、様々な実験を通じて把握できることを学んだ。特に馴化法などは「なるほど!」と思った。 その上で赤ちゃんは意外と早期に物理現象を理解していることや、自己像を理解していることを知った。さらに理解していても行動に表れないという現象が多くあることも知り、子どもを見るときは表面的な行動だけを基準とするべきでは無いことも理解できた。(この辺りのことは認知リソースの揺らぎに関係しているのかも) より一層我が子を観察したいと思うようになった。2020/12/01