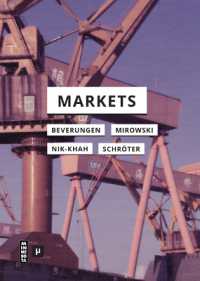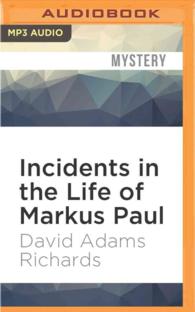- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
出版社内容情報
本書は、近代のジェンダーとセクシュアリティの規範がいかにして成立するのか、認定されるものとされないものがいかに策定されていくのか、変化し続けるその境界線の一瞬を記述しようとする試みである。(「はじめに」より)
「本書は、近代的なジェンダー規範が成立した明治四十年代から大正中期までを対象に、さまざまな女性の表現者たちが性をめぐる社会規範とどう交渉していったか、その個性的な様相をきめ細かく描き出した労作である。」(大塚明子氏評・3月23日/京都新聞)
内容説明
明治から大正期にかけて、消費文化の成立とともに登場した“新しい女”たち。彼女たちは社会に承認されるのか、“女であること”への抵抗は可能なのか。文学と演劇・ファッション・広告などの領域を超えて、ジェンダー規範の成立過程を明らかにした意欲作。
目次
第1部 「女」の魅せ方(もっと自分らしくおなりなさい―百貨店文化と女性;女が女を演じる―明治四〇年代の化粧と演劇、女性作家誕生の力学;再演される「女」―田村俊子『あきらめ』のジェンダー・パフォーマンス)
第2部 欲望と挫折(「けれど貴女!文学を捨ては為ないでせうね」―『女子文壇』愛読諸嬢と欲望するその姉たち;「一葉」という抑圧装置―ポルノグラフィックな文壇アイドルとの攻防;愛の末日―平塚らいてう『峠』と呼びかけの拒否)
第3部 身体という舞台(『人形の家』を出る―文芸協会上演にみる「新しい女」の身体;「新しい女」のゆくえ―宝塚少女歌劇と男性;医療のお得意さま―夏目漱石『行人』にみる悪しき身体の管理;封じられた舞台―文芸協会『故郷』以後の女優評価をめぐって)
著者等紹介
小平麻衣子[オダイラマイコ]
1968年生まれ。慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。博士(文学)。現在、日本大学文理学部教授。専門は日本近代文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。