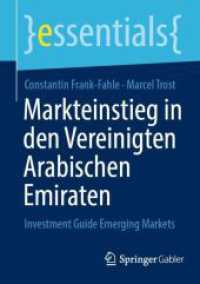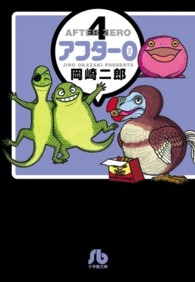出版社内容情報
里川とは里山をもじった造語。故郷の小川のイメージだけでなく、都会の川、街中の水路なども広く含みます。環境社会学・建築史・河川工学の視点から、日本中の川を三面コンクリートにした河川行政の行き過ぎを反省し、琵琶湖、熊本、愛知、山梨、東京下町などで川と人の深い結びつきを調査・取材。飲料水や農工業など経済目的の利水、水害の被害を防ぐ治水だけでなく、川を地域の財産、愛着ある場として共有する「守水」の考え方を「里川宣言」として提案しています。川の写真多数、豊富なブックガイド付き。
「里川」とは聞き慣れない言葉であろう。水について研究をしているわれわれプロジェクトチームの造語であるからである。現実に農業用水を里川と言っている地域があったので、それを借用したのである。したがって、造語というよりも借用語といった方が正確であろう。自分たちに身近な川として、前川とか、井川、村川というような命名が日本の各地に見られるが、里川もそのひとつである。(「序 いまなぜ里川なのか」より)
--------------------------------------------------------------------
【関連書籍】
『 コモンズをささえるしくみ 』 宮内泰介編 (定価2730円 2006)
『 みんなでホタルダス 』 水と文化研究会編 (定価2625円 2000)
『 環境的公正を求めて 』 戸田清著 (定価3675円 1994)
【新 刊】
『 関わる [生命誌]年刊号49-52 』 中村桂子編集 (定価1600円 2007.4月)
目次
序 いまなぜ里川なのか
第1章 里川の意味と可能性―利用する者の立場から
第2章 里川と異質性社会―あらそう人びと、つながる人びと
第3章 里川への経済学的アプローチ―矢作川の保全活動から
対談 他者との対話から生まれる川の物語
第4章 半自然公物としての里川―千年持続する河川技術から考える
対談 川への思い入れが拡げる新たな公
第5章 船旅による川の再発見
対談 「まち川」が多様な人びとを結びつける
第6章 書誌「里川」―文献で読む里川
終章 里川を求める思想―川とつきあいたい理由
著者等紹介
鳥越皓之[トリゴエヒロユキ]
早稲田大学人間科学学術院教授
嘉田由紀子[カダユキコ]
滋賀県知事
陣内秀信[ジンナイヒデノブ]
法政大学工学部建築学科教授
沖大幹[オキタイカン]
東京大学生産技術研究所都市基盤安全工学国際研究センター助教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
華凛。
taming_sfc