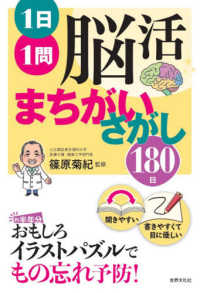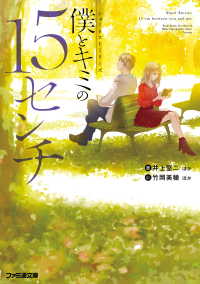出版社内容情報
ミミズの穴掘りから人間の言語・思考まで、心理学的なるものを有機体が世界と切り結ぶプロセス(アフォーダンス)に働く機能としてとらえ、それを生態と進化の観点から体系的に提示して話題を集めた気鋭の代表作。才気に富んだ囲み記事も楽しい。
内容説明
ゾウリムシからヒトまで、有機体が世界と切り結ぶ広大な「サイコロジカルなこと」の総体を、生態と進化の視点から論じ切った初の体系的な心理学教科書。
目次
はじめに 「サイコロジカルなこと」の地平へ
第1章 調整vs.構成
第2章 進化心理学
第3章 アフォーダンス:心理学のための新しい生態学
第4章 情報の重要性
第5章 機能系と行動のメカニズム
第6章 多様な行為システム群
第7章 価値と意味を求める努力
第8章 ヒトの環境
第9章 人間になる
第10章 心の日常生活
第11章 言語環境に入る
第12章 思考の流れ
おわりに 生態心理学の地平へ
著者等紹介
細田直哉[ホソダナオヤ]
1971年生まれ。東京大学文学部哲学科卒業、東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。主な著書に『アフォーダンスの構想』(東京大学出版会、近刊、訳・解説)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
4
ギブソンはゲシュタルト心理学から出発して光学から知覚システムを探求したが、著者はフロイトから出発して環境と知覚の不即不離な関係を無意識から捉え直す。ただし、過去に無意識の原因を見出すフロイトとは異なり、未来に動き続ける行為の無意識として。環境に利用可能な性質=アフォーダンスを探索する自己はアフォーダンスの群れに知覚の群れで対処する。コーヒーを飲む時、手や指はカップを持つためでなく、様々な無駄に見える振る舞いを経てカップに至る。フロイトが注意の欠如としたこの行為を、著者は試行錯誤的なマイクロスリップと呼ぶ。2017/09/21
kumazusa
3
古い本だけど新しい本だなと感じた。生態心理学的アプローチが必要になってくるのは理解できるが、どうやってそれを実現していくか、というのはとても難しいことだと思った。とても学際的な議論なので、いつかは生態心理学が主流になるのかもしれないけど、まだまだ先なのだろうなと感じた。私は工学系の人間なので認知主義になりやすいし、現在認知主義に基づいて研究を進めている感はあるけれど、指導教員も言うように、分布に基づいて判断しているのは確かだと思う。計測手法が発達したときに、認知主義はこの生態的アプローチと統合されると思う2013/04/01
大林ひろし
0
代表的なギブソニアン本。生態学的=エコロジカル=フィジカル+サイコロジカル。だから行動と意識は分離できない。だから刺激/反応、原因/結果といったモデルでは語れない。そして認知心理学に対して決定的な別れを告げる。世界を創造したのは人間である、というよりも神であると言った方が正しいのかも知れない。2012/10/14
かん
0
アフォーダンスの心理学とせず、原題の直訳の方が内容を理解しやすいのでは、と思いました。2009/02/28