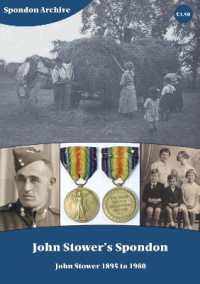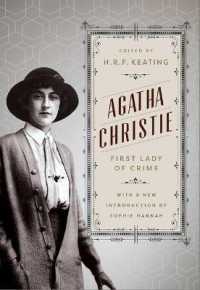出版社内容情報
性愛についての日本人の感覚,感受性はどのように変わってきたか,そしてその感覚はプロトコル(読みの規範)によってどのように規定されてきたかを,マンガ,ポピュラー音楽,映画,小説などを題材に辿る。系譜学的方法による近代日本の性愛の歴史。
本書はプロトコルという概念を提出したのだが、この考えは、今述べたような、イデオロギー/文化/声の複数性、そしてその響きあいの理論への、やや悲観的な修正である。私の説明モデルにおいては、二つのプロトコルが交錯した状況では、一方が他方を駆逐して統一される。複数のプロトコルが機能していると見えるのは、単なる見かけに過ぎない。明治二十年代以降のわれわれ日本人は、「好色」と「ドン・ファニズム」という二つのプロトコルを用いていると思いこんでいるが、「好色」の意味が変容して「ドン・ファニズム」と等価となっている以上、それは実は、「ドン・ファニズム」と「ドン・ファニズム」というトートロジーと戯れているに過ぎないのだ。われわれは二つの言語を同時に話すことはできないし、ふたつのプロトコルを同時に使って読む事もできないからである。(「複数のプロトコルにむけて」より
・「論座」98.7月号 特集「セクシュアリティを読み解く10冊」吉澤夏子氏
・「日本人の感情表現はどう変わったか」(毎日新聞 98.6.14 張 競氏評)
・「アエラ」98.3.2 特集「発情異常多発」 松原 慶氏
・「出版ニュース」98.2月号
・東京新聞 98.1.29
----------------------------------------------------------
【関連書籍】
『 迷走フェミニズム 』 E・バダンテール著 (定価1995円 2006)
『 季節の美学 身体/衣服/季節 』 塚本瑞代著 (定価3990円 2006)
『 肉対作品 』 P・ブルックス著 (定価5565円 2003)
内容説明
日本人の性愛の歴史。裸体はそれ自身がエロティックではない。文脈、プロトコル(通信条件、読みの規範)に応じて、まったく違った意味をもつ。江戸末から現代までの日本人の性愛の歴史をプロトコルの変遷として、文学、医学書から漫画、歌謡曲などのマス・カルチャーのなかに跡づける。
目次
序章 読みの規範としての「性」
第1章 恋人は友だち、妻は妹
第2章 二人のみゆき
第3章 子供と愛情
第4章 「心変わり」という制度
第5章 赤面する男
第6章 色男がドン・ファンに変わるとき
第7章 「性」の誕生
第8章 サド・マゾ・ファンタジーの成立
終章 複数のプロトコルに向けて
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kenitirokikuti
ともたか