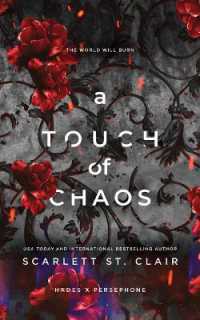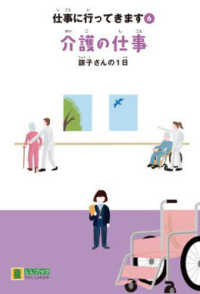出版社内容情報
保育所保育指針、幼稚園教育要領、こども園教育・保育要領の改訂の中で出される注目の書。子ども一人ひとりが、生活や発達に即して成長していくことを願い、取り組んできた保育活動の全体的な計画。
序章 日本における保育カリキュラム
第一章 日本における保育カリキュラムの誕生
第二章 保育問題研究会と「保育案」の研究
第三章 保育カリキュラムの展開ー和光幼稚園を中心に
第四章 集団生活の発展を軸とする保育
第五章 プロジェクト活動と保育カリキュラム
終章 改めて保育カリキュラムとは何かを考えるーまとめとして
宍戸健夫[シシドタケオ]
著・文・その他
目次
序章 日本における保育カリキュラム
第1章 日本における保育カリキュラムの誕生
第2章 保育問題研究会と「保育案」の研究
第3章 戦後保育カリキュラムの展開―和光幼稚園を中心に
第4章 集団生活の発展を軸とする保育
第5章 プロジェクト活動と保育カリキュラム
終章 改めて保育カリキュラムとは何かを考える―まとめとして
著者等紹介
宍戸健夫[シシドタケオ]
1930年横浜市に生まれる。1959年東京大学大学院人文科学研究科教育学専攻博士課程修了。博士(教育学)。1966年愛知県立大学定年退職。同大学名誉教授。現在、佛教大学教授を経て、同朋大学客員教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
25
日本の保育カリキュラムについて戦前から今日までの歴史を振り返りながら子どもの発達の視点から課題は何かを考察した大変重みのある本だと思いました。保育カリキュラムは保育者たちが子どもの生活や発達に即して将来への願いを込めてつくられます。こうした保育計画は日々の保育実践によって常に省察されているものだと思います。そうしたなかで日本の保育者たちが特に集団保育実践を積み上げていくなかで何に苦労し、どのように子どもたちに寄り添っていったのかを考えることができました。もっと勉強する必要も痛感しました。2017/09/16