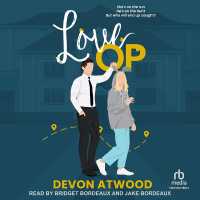目次
第1章 日本における幼稚園の誕生
第2章 明治一〇年代における幼児保育政策―簡易幼稚園の奨励
第3章 はじめての簡易幼稚園―女子高等師範学校附属幼稚園の分室
第4章 貧しい子どもたちのための二葉幼稚園―幼稚園から保育園へ
第5章 児童保護事業の展開―石井十次、冨田象吉、大原寿恵子
第6章 岡弘毅の保育一元化論―幼稚園令と託児所令(案)
第7章 公立保育園の誕生―慈善事業から社会事業へ
著者等紹介
宍戸健夫[シシドタケオ]
1930年横浜市に生まれる。1959年東京大学大学院人文科学研究科教育学専攻博士課程修了。博士(教育学)。1996年愛知県立大学定年退職。同大学名誉教授。現在、佛教大学教授を経て、同朋大学客員教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
13
この本は、明治期の幼稚園誕生から大正期の公立保育園の設立に至るまでの歴史が展開されたものです。日本の保育は、子どもの貧困などの社会問題に対して社会的使命を持って生み出されてきたのだと学べました。同時に、ただ預かるのではなく、施設のあり方や実践のあり方なども研究され、発達の視点も持つものであったのだと学べました。歴史に学ぶことはとても重要です。こんにち、保育が市場化・営利化されようとしている中で、公立保育園の誕生までの歴史を学ぶことは、とても大切ではないかと思いました。2014/09/09
昌也
0
保育の歴史は子どもの貧困の歴史なのか?2021/10/03