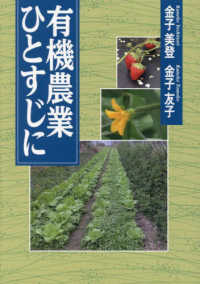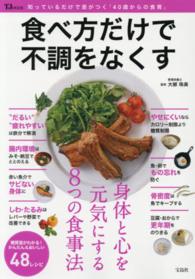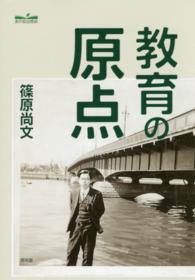内容説明
フレーベルとその門下生たちの「恩物」と「作業」に関わる理論と実際を、草創期の幼稚園ではどのように受け取り、実践しようとしたのか。保姆たちが、幼児にわかりやすいように教える工夫をしたり、幼児たちが喜ぶことを取り入れようとする様子から、実践から学ぶことの重要性が浮かびあがる。手技の理論と実際を歴史的に明らかにした。
目次
第1章 明治時代1―明治10年代前半(1881年)まで
第2章 明治時代2―10年代後半(1882年)から20年代
第3章 明治時代3―30年代(1897年~1906年)の手技
第4章 明治40年代(1907年)から大正時代(1915年)にかけての手技
第5章 大正時代終わり(1926年度)までの手技
第6章 昭和11(1936)年度までの手技
第7章 昭和12(1937)年度から終戦までの手技
著者等紹介
清原みさ子[キヨハラミサコ]
1948年東京都生まれ。1971年お茶の水女子大学文教育学部教育学科卒業。1973年お茶の水女子大学大学院人文科学研究科教育学専攻修士課程修了(文学修士)。1973年以降、九州文化学園短期大学講師、九州大谷短期大学講師、愛知県立女子短期大学兼愛知県立大学講師、愛知県立大学教授を経て、愛知学泉短期大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。