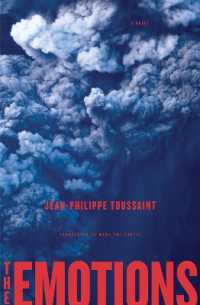目次
序 保育とは子どもに良質な記憶を創ってあげること(関係が悪い方が喪失の悲しみが続く;楽しい記憶が死別をのり越える力になる ほか)
第1章 気になる子を好きになる(苦手な子どもに声かけする養護教諭;先手必勝の発想 ほか)
第2章 「気になる子」と自制心(気になる状況に注目する;ささいなことで気分が崩れて大泣きする ほか)
第3章 落ち着きがない子への援助(発達相談で出会った、落ち着いた子ども;麻痺を持つ子どもは、気持ちの流れを尊重されにくい ほか)
著者等紹介
浜谷直人[ハマタニナオト]
1953年富山県生まれ。東京大学大学院博士課程単位取得退学。現在東京都立大学人文学部教授。学校心理士、臨床発達心理士、臨床心理士。保育園、幼稚園、学校、学童クラブへの発達臨床コンサルテーション(巡回相談)活動を続けている。困難をかかえた子どもが、生活の場に十全に参加することを支援してきている
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ごん
1
「語りたい経験(記憶)をつくることが自制心を育てる。」 自制心とは「自らの豊かな要求を、周囲の状況と調整しながら、粘り強く実現する心のはたらき」2014/08/29
akagiteaching
1
「保育とは子どもに良質な記憶をつくること」というメッセージに感涙。「将来,困らないように今を犠牲にしてでも能力形成を」的な特別支援教育語りとは,真逆。「未来に踏み込んでいけるのは,あのときの保育園や学校,授業が楽しかったからなんだ」という主張。どうとるかは人それぞれ。実証的にもこれから。ただ少なくとも「あのときの先生の授業楽しかったなー」という原体験は,その人を幸せにすると思う。2013/06/03
かいち
0
保育者が先手をとるというのはとても面白い!!事後的にまわってしまうからこそ、ダメというワードを必要以上に口にすることも増えてくるのかもしれない。あと「生き生きとした見通し」という表現は多いに共感。機会的な見通しとの違いをこれから実証的に示していけたらなあと僕も思いました。2013/06/09
ごん
0
読んだことをまとめるために再読。 やっぱりバイブル。メモすることが多すぎてA4で5枚になってしまった^^;2022/01/31
-

- 電子書籍
- 特命係長 只野仁 デラックス版 4
-
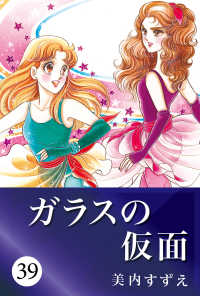
- 電子書籍
- ガラスの仮面 39